本の世界
本の世界
2019年08月29日(木)
 人体 神秘の巨大ネットワーク
人体 神秘の巨大ネットワーク
丸山優二著
NHKスペシャル「人体」取材班
www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20171001
NHK出版新書
2019年5月10日発行
900円
本書は、NHKスペシャル「人体 神秘の巨大ネットワーク」シリーズで放送された内容をおさらいしつつ、さらに掘り下げたもの。 続きを読む
2022年08月16日(火)
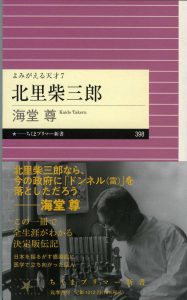 よみがえる天才7
よみがえる天才7
海棠 尊 著
ちくまプライマリー新書
2022年3月10日発行
920円
座右の銘は「任人勿疑、疑勿任人」(人を疑うに任ずるなかれ、人を任じて疑うなかれ)
あだ名は「ドンネル(雷)」
医学は、誤解と誤謬を是正しながら築き挙げられていくもの。彼の人生を理解することは、現在の衛生行政の誤謬を理解する一助となる。北里が直面していた問題は、決して過去のことではない。 続きを読む
2025年01月26日(日)
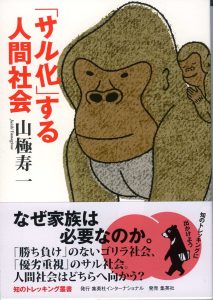 山極寿一著 京都大学総長 理学博士
山極寿一著 京都大学総長 理学博士
集英社
2014年7月30日発行
1100円
人間社会のリーダーは、ボス化している。
サル社会は、「上下関係」「優劣」「勝ち負け」がハッキリとしている。ボスザルを頂点としたピラミッド序列。自分の地位を脅かそうとする相手を徹底的に排除する。それも、力や地位を利用した方法を取る。食べる時は分散して、互いに目が合わないようにする。
一方、ゴリラの社会には「優劣」がない。喧嘩に「勝ち」も「負け」もつけない。群れのリーダーがメスや子供と食物を分け合うのはごく「当たり前」のことで、しかも「向き合って食事をする」。
続きを読む
2025年10月11日(土)
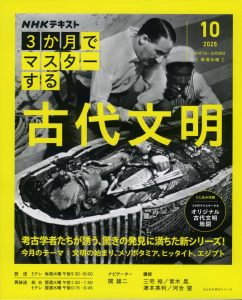 NHK3か月でマスターする
NHK3か月でマスターする
古代文明 10月号
2025年10月1日発行
NHK出版
1430円
mag.nhk-book.co.jp/article/79132
www.nhk.jp/g/ts/3JYG9W8MQ5/
ギョベックリ・テペから見つかる“古代の記録”は、これまで私たちが“常識”として考えていた文明の始まりに対して、全く異なる視点を与えてくれている。 続きを読む
2023年11月12日(日)
 -ハルマッタンの風に運ばれて-
-ハルマッタンの風に運ばれて-
著者 池田憲昭
口腔保健協会
2023年9月30日
1800円
若いときの出会いは大切。それを受け取れる素晴らしさに感動。
池田憲昭氏講演会
「開発途上国における保健システム強化支援について」2008年10月19日
kojima-dental-office.net/20081019-2742#more-2742
格差社会において20年以上グローバルヘルスの現場で「派遣された国の人たちが公平に適切な保健サービスを受けることが可能になるような行政の強化や仕組み作り」を現地の人たちと共にしてきたと私は思っている。しかし、パンデミックの今は、経済的格差がむしろ拡大するという現実に直面している。 続きを読む
2018年07月16日(月)
 昭和大学 名誉教授 向井美恵
昭和大学 名誉教授 向井美恵
kojima-dental-office.net/20060723-1429#more-1429
ぜんほきょう 2018年6月号
全国保育協議会 続きを読む
2025年05月29日(木)
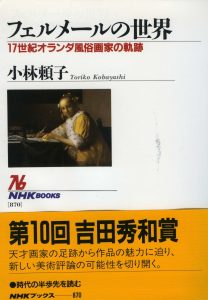 17世紀オランダ風俗画家の軌跡
17世紀オランダ風俗画家の軌跡
小林頼子著
1999年10月30日発行
NHKブックス
1160円
オランダ風俗画から見えてくる日常生活に心が躍り、フェルメール絵画の中に流れる不思議な時間に魅了される。フェルメールは、行為の伴わぬ単身の風俗画という新たな独自の世界を、貪欲なまでの模倣の精神と豊かな創造的エネルギーによって描き始めてわずか数年で創り上げた。考え抜かれた消失点・消失線、遠隔点・対交線に基づいた空間構成法によって視覚印象との不自然さを解消させ、光と質感の描写も独特のものへと鍛え上げた。1675年に43才という若さでこの世を去った彼にもう少し時間があったなら、どんな作品に進化しただろうか。
17世紀オランダは、他のヨーロッパ諸国に先駆けて市民主体の社会が実現し、国教と定められたプロテスタントが基本的に教会内を宗教画で飾ることを禁止していたので、絵画の購入層が王家、貴族、教会といった大口の顧客ではなく、市民、農民といった一般の人々だった。だから小さな絵が多く、庶民の日常の姿を反映する風俗画が好まれた。 続きを読む
2023年06月24日(土)
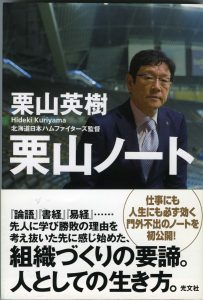 栗山英樹著
栗山英樹著
光文社
2019年10月30日発行
1300円
参考に
歯科関連ニュース 5.4.14.【7】WBC優勝 栗山英樹監督に学ぶ
kojima-dental-office.net/20230414-6934
野球ノートをつける習慣
小学校1年から野球を始めた。小学校当時は、その日の練習メニューを書き出したり、気になったプレーを図解したりしていた。中学から高校、高校から大学と野球を続けていく中で、ノートと向き合う気持ちは変わっていく。チームが勝つためにどうすればいいのか、という考えが織り込まれていく。テスト生でヤクルトスワローズに入団してからも、練習後や試合後にノートを開くことは習慣化されていたが、自分のプレーを整理できず、書けない日もあった。
学生時代から本には親しんできた。本を読んでいくうちに、成功を収めたと言われる人たちの共通点は、古典に当たっていること、『四書五経』、『論語』、『易経』、『韓非子』といったものの教えが時代を超えて模範的で普遍的な価値を持つこと、に気づいた。2012年に北海道日本ハムファイターズの監督になってからは、リーダー論や組織論などのビジネス書にヒントを求めることが多くなった気がする。野球ノートをつけることと、古今東西の古典を中心とした読書の旅を並行していくと、野球を野球の常識だけで読み解くべきではないという思いに辿り着く。 続きを読む
2008年11月28日(金)
勢古浩爾著
洋泉社 新書
2004年12月20日発行
740円
白州次郎は、「日本一カッコイイ男」といわれ、理を助け無理に歯向かう男である。理を知りながら、情を失わない。一言で言うと、実がある。また、自分の非を認めてきちんと謝罪できる男でもあった。そして、権力に望んだことは「雅量と同情」である。 続きを読む
2022年12月11日(日)
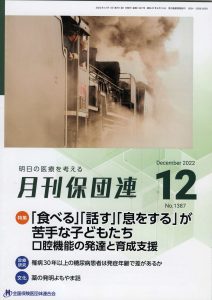 月刊保団連 2022年12月号
月刊保団連 2022年12月号
特集「食べる」「話す」「息をする」が苦手な子どもたち
口腔機能の発達と育成支援
現代日本人の歯並びが最悪なワケ
人類学から考える咀嚼期の発達と退縮
国立科学博物館人類研究部名誉研究員 馬場悠男 著
人類は、道具使用と肉食によって咀嚼器を退化させた。その過程で、喉頭が頸まで下降し、睡眠時無呼吸の究極要因が生まれた。ただし、その後でも、例えば縄文人は、歯列が広くて歯並びがよく、正常な口腔容量を保っていたので、睡眠時無呼吸を起こすことはなかった。ところが、現代日本人では、歯並びが極端に悪くなり、口腔容量が不足し、しばしば睡眠時無呼吸を起こす。 続きを読む

