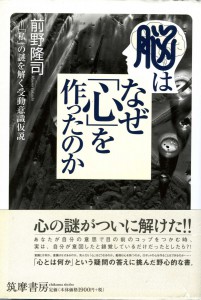本の世界
本の世界
2023年11月15日(水)
 「仕事が速い人」になる時間術101
「仕事が速い人」になる時間術101
著者 理央 周
日本実業出版社
2023年3月10日
1400円
不機嫌な人はコミュニケーションコストが高く、ご機嫌な人は低い
コミュニケーションコストとは、情報の伝達・意思疎通にかかる時間や手間のことを指す。同時に、報告・連絡・相談など、ルーティンで必要な情報共有にかかる手間を指す。
不機嫌な人は、周囲の人が話しかけるのをためらうので、報告やアドバイスなどの情報がタイムリーに集まりづらくなってしまう。反対に、ご機嫌な人は、人から話しかけてもらいやすく、情報も集まってきやすくなり、いい提案も生まれやすくなる。
順位や年齢が上がるほど、気を遣われるようになるため、コミュニケーションコストは高くなる傾向がある。 続きを読む
2009年03月06日(金)
藤原 正彦著
新潮新書
2005年11月20日発行
680円
アメリカ化により、金銭至上主義に取り憑かれた日本人は、財力に任せた法律違反すれすれのメディア買収を、卑怯とも下品とも思わなくなってしまった。戦後、祖国への誇りや自信を失うように教育され、すっかり足腰の弱っていた日本人は、世界に誇るべき我が国古来の「情緒と形」をあっさり忘れ、欧米の「論理と合理」に身を売ってしまった。「国家の品格」をなくしてしまった。振れすぎた振り子を見直し、日本人の心を取り戻していただきたい。 続きを読む
2008年08月05日(火)
 著者 山田 規畝子
著者 山田 規畝子
発行 講談社
体裁 254頁・B6判
本体価格 1600円
発行 2004年2月26日
医師という病気を診るプロが、身をもって体験した自分の病気(認知障害)について書きとめた書である。三度の脳出血、その後遺症と闘う医師の生き方と「からっぽになった脳」を少しずつ埋めていく「成長のし直し」の記録である。自分の脳を、偉いなあ、と愛してあげて、一生懸命使ってくれる若者がひとりでも増えることを願っている。日ごろ診ている患者さんのいる世界かも知れないのに、想像したこともなかった。 続きを読む
2008年08月11日(月)
今で考えたこともない角度からの「心」について内容は、小びとたちを総動員、フル回転しても難解でした。皆さんも挑戦してみてください。
心は、小びとたちが織りなす巨大な連想ゲームの世界と、それを意識していると錯覚している「私」から成る。心を説明できるということは、死後の世界があり得ない。すべての喪失である死を明確な前提として生を考えなければならない。 続きを読む
2008年08月11日(月)
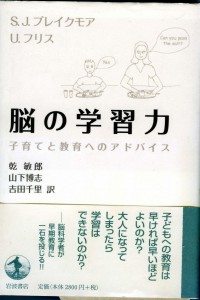 子育てと教育へのアドバイス
子育てと教育へのアドバイス
S.J.ブレイクモア、U.フリス 著
乾 敏郎、山下博志、吉田千里 訳
岩波書店
2800円
2006年10月17日発行
ここ数年、脳に関する本の出版が相次いでいる。しかし、現時点でわかっていないことや実証されていないことをここまではっきり書いている本は少ないと思う。教育者と脳科学者との交流がはじまり、最近の技術革新により脳の機能が明らかになり、脳と学習に関する研究がここまで進んでいる。医療、教育を始め、さまざまな分野の人々に読んでいただきたい1冊である。 続きを読む
2011年12月08日(木)
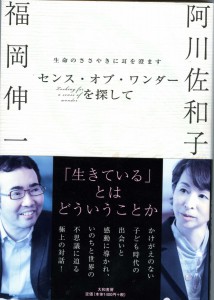 生命のささやきに耳を澄ます
生命のささやきに耳を澄ます
福岡伸一 阿川佐和子著
大和書房
2011年11月1日発行
1400円
人間にとって子ども時代とは、生きるとは何なのかを深く考えさせられる1冊である。そして、機械論的にこだわらず動的平衡も視野に入れて患者さんと向き合いたいと思う。
また、2人の対談からインタビューの秘訣も学んだ。質問をひとつだけ用意する。その答えをじっくり聞き、答えの中に次の質問を見つける。
生物と無生物のあいだ
kojima-dental-office.net/blog/20200914-14306#more-14306
動的平衡
kojima-dental-office.net/blog/20180814-10323#more-10323 続きを読む
2024年07月23日(火)
 外国人が見たニッポン
外国人が見たニッポン
著者 鴻上尚史
講談社現代新書
2015年4月20日発行
900円
番組では毎回テーマを決めて8人の外国人と一緒に話し合う。タレントではなく、学生や仕事で日本に来たり、夫と共に赴任した人たち。
相手を知り、自分の国のことを具体的に知ることは、やがて、自分自身を知ることにつながる。世界にはこんな見方があり、こんな考えがある。多様であることを楽しむことは、きっと自分自身の人生も豊かにし、深くすることになる。 続きを読む
2021年10月27日(水)
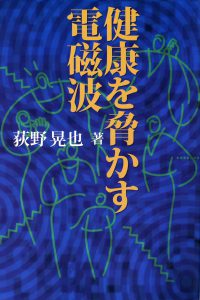 荻野晃也著
荻野晃也著
2007年5月10日発行
緑風出版
1800円
20年ほど前から送電線・変電所・配電線などの電力施設や家庭の電気製品などから漏洩してくる交流の低周波電磁波が、私たちの健康に悪い影響を与えるのではないかと言われ始めた。電磁波による影響には、白血病・脳腫瘍・乳ガン・肺ガン・アルツハイマー病が報告され、ノイローゼや自殺も関係があるといわれている。電磁波の健康への悪影響が完全に確定したわけではない。しかし、欧米では、「危険な可能性が高いのなら慎重に回避しようではないか」という「慎重なる回避思想」「予防原則思想」が広まっている。スウェーデン政府は、国レベルで「悪影響がある」と判断し、1992年末から具体的な対策を取り始めている。スイスやイタリアでは厳しい基準値を作り始めた。イギリスでは、16才未満には携帯電話を使わせないようにしている。 続きを読む
2025年04月04日(金)
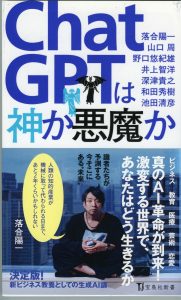 著者 メディアアーティストの落合陽一
著者 メディアアーティストの落合陽一
著作家・パブリックスピーカーの山口周
経済学者の野口悠紀雄
経済学者・駒澤大学経済学部準教授の井上智洋
インタラクション・デザイナーの深津貴之
精神科医・立命館大学生命科学部特認教授の和田秀樹
生命学者・早稲田大学名誉教授の池田清彦
宝島新書
1100円
2023年10月11日発行
本書では、各分野を代表する7名の識者が徹底検証する。
ChatGPTの操作はとても簡単で、誰でも直感的に使うことができる。時代に取り残されないためには「新しいものに触れる」という興味関心と行動力が大切。使い方はアプリをダウンロードして、質問を打ち込むだけ。できれば有料版で試してみよう。質問の仕方を工夫することで、より具体的かつ望ましい回答に近づけることができる。 続きを読む
2009年01月01日(木)
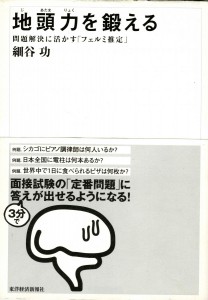 問題解決に活かす「フェルミ推定」
問題解決に活かす「フェルミ推定」
細谷 功著
東洋経済新報社
2007年12月20日発行
1600円
「日本全国に電柱は何本あるか?」
コピペ族が氾濫し、考える能力がますます退化していく現代において、人材確保のために利用している企業の面接問題である。考える手がかりもほとんど無い状況下で、3分以内に答えを出す。結果の正確さではなく、思考のプロセスを試す問題である。
また、「フェルミ推定」を使って地頭力を鍛えよう。自分なりに答えを出してページをめくり、答えを読むWhy型の好奇心を持ってこの本にチャレンジしていただきたい。 続きを読む