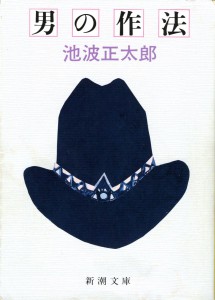本の世界
本の世界
2024年01月05日(金)
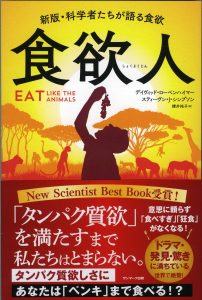 新版・科学者たちが語る食欲、健康的に食べる方法を、動物が教えてくれる
新版・科学者たちが語る食欲、健康的に食べる方法を、動物が教えてくれる
著者 デイヴィット・ローベンハイマー
スティーブン・J・シンプソン
訳者 櫻井祐子
サンマーク出版
2023年6月30日発行
1600円
科学者は、「自分は間違っていないだろうか」と常に自問するよう訓練されている。研究で特殊例にとらわれすぎると、結果に潜む真のパターンを見過ごすリスクがある。また、自分の見たいものしか見ないリスクもある。そこで役に立つのが統計学。データの乱雑さやバラツキの根底にパターンが存在する場合、それを見抜く上で統計学は欠かせない。 続きを読む
2021年12月27日(月)
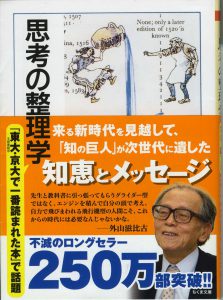 外山滋比古著
外山滋比古著
ちくま文庫
1986年4月24日発行
2021年3月5日 第125刷
520円
1.「思われる」と「考える」
①I thinkAisB
日本へ来たばかりのアメリカ人から、「日本人は二言目にはI think….というが、そんなに思索的なのか」と質問されて、面食らうことがある。
「AはBである」と断定してしまっては、相手へのあたりが強すぎるという気持ちが働く。そこで何かで包みたい。人にお金を渡す時に包みに入れる感覚。「むき出しのお金はいけない」は常識。「AはBである」は、はしたない。包めば「AはBだと思う」となる。その心理が英語でしゃべる時に持ち込まれると、AisBではなく、特に考えているわけではないのにI thinkAisBという表現になる。 続きを読む
2009年10月25日(日)
池波正太郎の「若い友人」佐藤隆介氏の様々な質問に答えられたものが、きわめて具体的に男の生き方を教えるこの一冊になっている。食卓の礼儀作法に始まり、人事、組織、贈り物、小遣いなどなど。引き戸や畳などの日本の家についても語る。自分を知り、自分本位ではなく、他人を思いやり、気をまわす日本の心に触れたように思う。 続きを読む
2021年01月26日(火)
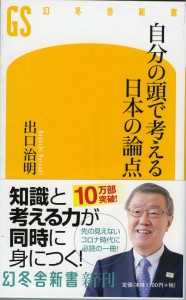 出口治明著
出口治明著
立命館アジア太平洋大学学長、ライフネット生命創業者
幻冬舎新書
2020年11月25日発行
1100円
人々の間で意見が分かれている「論点」を22個選び、基礎知識的なことを解説した上で、著者はどう考えているかを述べている。そこに至る思考のプロセスを学びたい。
物事を考える時に大切にされていることは、「タテ(昔の歴史)・ヨコ(世界はどうなっているか)・算数(数字、事実、論理で裏付ける)」の3つ。日頃からそのような訓練を積み重ねることが、想定外のことが起きた時に生き残る力とななる。
続きを読む
2020年12月11日(金)
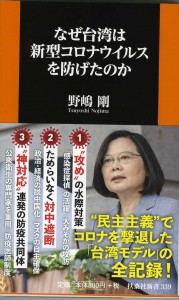 野嶋剛著
野嶋剛著
nojimatsuyoshi.com/
扶桑社新書
2020年7月1日発行
880円
・SARSの教訓から指揮系統の一本化、中央と地方の一致、対策の合理性、情報の透明化、必要な準備、法体系の整備などの事前対策をしっかリ整えたこと
・12月31日に、台湾政府は、情報の把握、閣僚会議、検疫体制の強化、中国への確認、WHOへの通報、そして、国民への注意喚起を行ったこと
・トップが大局的観点から決断できたことと、これと思った人材を揃えることができる仕組みがあること
・「台湾を守る」への共感力が台湾のコロナ対策の原動力になったこと
・インターネットの無数の議論から生まれる世論上の判断が政策決定に活かされること
・台湾では、まずは国民の生命を守る感染押さえ込みを優先し、政府に保証や支援を求める「金」の話は後で構わないという考え方が強かったこと
・感染症対策については、国家は鬼になったこと
・台湾の人々は中国とWHO情報を信用しなかったこと
・ITに強いこと
などなどジャーナリストの分析はすごい。
時系列もお読みください 続きを読む
2021年09月11日(土)
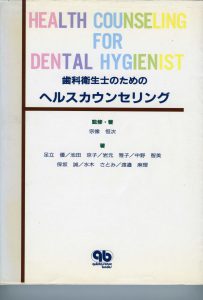 宗像恒次監修・著
宗像恒次監修・著
1998年1月10日発行
クインテッセンス出版
6500円
本書で述べるヘルスカウンセリングは患者さんが必要な行動改善に自ら気づき、自分の意思によるセルフケア行動を育てるための行動科学に基づいた効果的な係わり方である。
頭で分かっていながら行動の決断と実行ができない背景には、不安、怒り、悲しみなど隠された感情を持った意思が働いていて行動を妨げている。歯科医療従事者は患者さんの隠された感情や意思に気づき、自分自身で決断できるように支援できるカウンセリング技法を身につける必要がある。 続きを読む
2009年04月16日(木)
サイズの生物学
本川達雄著
1992年8月25日発行
中央公論社
680円
読み継がれてきたことに納得できる本である。
動物が変われば時間が変わるということを知った時は、新鮮なショックを感じた。時間が違うということは、世界観がまったく異なるということである。時間とは、最も基本的な概念である。しかし、自分の時計は何にでも当てはまると、なにげなく信じ込んで暮らしてきた。そういう常識をくつがえしてくれるのが、サイズの生物学である。一生を生き切った感覚は、ゾウもネズミも変わらないのではないかと思う。
サイズを考えるということは、ヒトというものを相対化して眺める効果があり、ヒトの自然での中の位置を知ることが出来る。人が己のサイズを知る、これは人間にとって、最も基本的な教養であろう。 続きを読む
2008年07月31日(木)
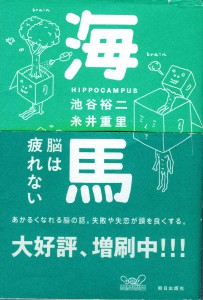 池谷裕二先生とコピーライターの糸井重里氏との対談
池谷裕二先生とコピーライターの糸井重里氏との対談
2004.6.1.
池谷裕二 1970年生まれ 東京大学薬学部助手
1998年 海馬の研究により薬学博士号を取得
糸井重里 コピーライター
朝日出版 1700円 続きを読む
2024年09月29日(日)
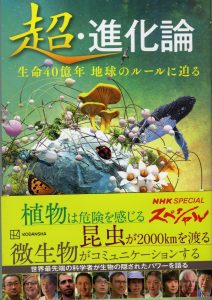 生命40億年 地球のルールに迫る
生命40億年 地球のルールに迫る
著者 NHKスペシャル取材班+緑慎也
講談社
2023年3月6日発行
1800円
[NHKスペシャル] 植物たちには「おしゃべり」をする能力
www.youtube.com/watch?v=94OKuOrqalg&list=PLcynJ47QaWNsHJRVIupWyZEljIsGqhUGL&index=14
植物という不思議な生き方
kojima-dental-office.net/blog/20080814-1149#more-1149
NHKスペシャル「超・進化論」のきっかけは、植物が、他の植物や昆虫たちと、まるで“会話”をするように、離れた相手にメッセージを送っている、コミュニケーションをとっているという研究だった。ディレクター・制作統括 白川裕之は、多様な生命の共存を支える“地球のルール”と“生物多様性の本当の姿”に迫る大型プロジェクトの取材をスタートさせた。 続きを読む
2026年02月18日(水)
 イギリス植民地から多民族国家への200年
イギリス植民地から多民族国家への200年
著者 竹田いさみ・永野隆行
2023年2月25日 発行
中公新書
1000円
日本とオーストラリアとの関係を歴史順に解説しているところが素晴らしい。特に、日英同盟の第1次から3次への論理的な変遷とその考察が鋭い。イギリスの巧みさ、駆け引きを学ぶ。それを見習うオーストラリアが独自の道を切り開く。論理ですべてを貫く欧米と、論理的に正しいことと善悪は別次元であると教える日本との違いを感じる。
オーストラリア人の考え方や価値観と、イギリスがオーストラリアを発見した18世紀後半から現代までの山あり谷ありが面白い。オーストラリアが植民地から自立へ、そして労働党と自由党の時代とともに交互に変わる生き抜く姿、イギリス追従から安全保障をアメリカに委ねる決断など。 続きを読む