フェルメールの世界
2025年05月29日(木)
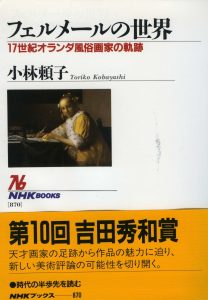 17世紀オランダ風俗画家の軌跡
17世紀オランダ風俗画家の軌跡
小林頼子著
1999年10月30日発行
NHKブックス
1160円
オランダ風俗画から見えてくる日常生活に心が躍り、フェルメール絵画の中に流れる不思議な時間に魅了される。フェルメールは、行為の伴わぬ単身の風俗画という新たな独自の世界を、貪欲なまでの模倣の精神と豊かな創造的エネルギーによって描き始めてわずか数年で創り上げた。考え抜かれた消失点・消失線、遠隔点・対交線に基づいた空間構成法によって視覚印象との不自然さを解消させ、光と質感の描写も独特のものへと鍛え上げた。1675年に43才という若さでこの世を去った彼にもう少し時間があったなら、どんな作品に進化しただろうか。
17世紀オランダは、他のヨーロッパ諸国に先駆けて市民主体の社会が実現し、国教と定められたプロテスタントが基本的に教会内を宗教画で飾ることを禁止していたので、絵画の購入層が王家、貴族、教会といった大口の顧客ではなく、市民、農民といった一般の人々だった。だから小さな絵が多く、庶民の日常の姿を反映する風俗画が好まれた。 レンブラント(1606~1669)の闇に輝く光を真昼間の白日の光に変え、洞窟のような空間を家庭の一室に移せば、フェルメール(1632~1675)の作品が見えてくる。レンブラントが描いた肖像画を見ると、女性の身につけている衣装はほとんど黒いことに気づく。カトリックの信仰を護持しようとするスペインの支配下では黒の服が好まれたが、その終焉とほぼ同じくして、中・上流の人々が好む美しい衣装を楽しむ頃にフェルメールが風俗画を描き始めた。フェルメールが、『真珠の耳飾りの少女』の魅惑的な青がピンポイントの時に選ばれた。
レンブラント(1606~1669)の闇に輝く光を真昼間の白日の光に変え、洞窟のような空間を家庭の一室に移せば、フェルメール(1632~1675)の作品が見えてくる。レンブラントが描いた肖像画を見ると、女性の身につけている衣装はほとんど黒いことに気づく。カトリックの信仰を護持しようとするスペインの支配下では黒の服が好まれたが、その終焉とほぼ同じくして、中・上流の人々が好む美しい衣装を楽しむ頃にフェルメールが風俗画を描き始めた。フェルメールが、『真珠の耳飾りの少女』の魅惑的な青がピンポイントの時に選ばれた。
また、レンブラントは、莫大な家のローンを抱え、不労所得もなく、稼がなくてはならなかったので、年に10点ほどのペースで作品を制作しなければならなかった。一方、フェルメールは、義母の家に同居し家賃を払う必要もなく、相続した不労所得や画商としての副収入もあり豊かさを享受していたので、年に2~3点というゆっくりとしたペースで、構図を緻密な計算の上に決定し、細部にいたるまで丁寧に仕事をしていた。
オランダ・ベルギーの旅 7つの美術館や教会巡り2025.5.12.~22.
kojima-dental-office.net/blog/20250522-21619
上野の森美術館フェルメール展 2018年10月23日
kojima-dental-office.net/blog/20181025-10612
A.オランダの画家
オランダ絵画は、ネーデルランド南部、フランドルから移住してきた画家たちの活躍があって17世紀に黄金時代を築き上げた。
1.物語画家
1588年に成立したオランダ共和国が市民国家だったから、オランダの画家は、他のヨーロッパ諸国とは異なり、王家、貴族、教会といった大口の顧客を持っていなかった。国教と定められたプロテスタントは基本的に教会内を宗教画で飾ることをタブーとしていた。したがって、物語画家として大型の歴史画や神話画の注文を当てにして生計を立てられる状況ではなかった。
オランダの当時の画家たちは、稀に注文を受けて制作することもあったが、買い手の顔の分からぬ美術市場に向けて仕事をすることのほうが圧倒的に多かった。つまり、画家として得られる彼らの収入は、時々の市場経済の並に左右される、極めて不安定なものになっていた。
そうした状況への対処策が、特定の絵画ジャンルを専門とし制作の効率化を図ることだった。もう一つ別の手立ては副業を営むことだった。副業に選ばれる職業としては、宿屋、画商が目立って多い。買い付けにも質の見定めにも格別の訓練を必要としない画商業は、ごく自然の選択だった。
2.風俗画家
1648年にミュンスター講和の締結でスペインとの戦争状態もようやく終わりを告げた。以降、オランダ市民は16世紀末から蓄積してきた富を背景に平和で豊かな生活をしばし楽しむことになる。こうした生活の変化が、絵画の受容層を市民、農民といった一般の人々にまで徐々に広げていき、王侯貴族好みの大画面の物語画よりも、庶民の日常の姿の新たな画題を要求させた。画家たちも、物語画とは別の分野、オランダ特有の小さな風俗画、静物画などの市民的ジャンルに活路を求めた。
修道院生活や僧侶の独身制度が廃止されたプロテスタントの国オランダで、社会の中心が教会から家庭へと移っていった。社会の大きな変革により、家族や家庭の重要性が増したことによりオランダの風俗画が変わった。倫理観と道徳心を養い、まっとうな人間を育てる場は、教会ではなく、清潔で健全な家庭生活に求められるようになった。そうした家庭には、露悪的、享楽的な情景を大胆な筆遣いで描いたかつての風俗画ではなく、新たなる家庭観を反映する室内を繊細なタッチで描き上げた新しいタイプの風俗画こそふさわしかった。
B.風俗画が語る社会史
17世紀オランダの絵画は、描かれている人物の服装、その営み、室内や街の様子など当時の日常生活を色濃く反映している。とりわけ顕著なのは風俗画。絵画の中の世界と現実世界は、限りなく近づき、重なり合っている。作品が歴史的所産である。
フェルメールの作品でも事情は変わらない。画面構成法には他の画家とは異なる試みや狙いが認められるが、描き取られた個々のモティーフは他の画家との間に違いはほとんどない。娼家の様子、家事を任された女中の存在、清潔きわまりない部屋の様子、サテンをふんだんに用いた洒落たファッション、音楽や読書を楽しむ中流階級の女たち、机に向かって仕事をする男たちなど当代の日常の暮らしを彷彿とさせるものばかり。
1.召使いの女たち
当時、オランダの全所帯のうち、10~20%が召使いを一人は抱えており、そのほとんどが女性であった。オランダの全人口の6%を占めた召使いの女たちは、たいてい地方の貧しい少女たちで、平均2から3年勤めた後、より高い給料を求めて奉公先を変えるのが普通だった。
召使いの女たちの働きぶりは2つのタイプに分けられる。先ずは、女主人を従順にサポートし、課せられた務めを勤勉に果たし、しかも奉公先の家族の人たちとも良好な関係を保って仕事をする召使い。2つ目のタイプは怠情で堕落した召使い。
①フェルメールの描く召使い
当時の記録辿っていくと、召使いの弱者としての姿が浮かび上がってくる。
フェルメールの描く召使いは、きわめてニュートラルな、モラルの枠組みの外にいる人物として扱われている。淡々と空間の枠組みづくりに協力するだけで、社会的な既成概念を表出しかねなかった召使いも、フェルメールの手にかかれば、たちまち弱者か否かの判断を超越した存在へと変わってゆく。 フェルメールの絵には社会的な背景を知りたくなるような関心を掻き立てるものがほとんどない。不思議な図像処理である。
2.17世紀の身体表現
農民を描いた絵では腰を曲げ、背中を丸め、首をかしげているのに対し、17世紀半ば以降に描かれた風俗画には、壁の近くに背筋をピンと伸ばして立つ姿勢のいい若い女が多い。この姿勢の良さは、上層階級の習慣を反映したものであり、中流市民の意識を巧みに吸い上げた結果である。
近代初期のヨーロッパでは、首と背を伸ばし直立した姿勢を保つことは作法を知る人間の極めて重要な要件とされていた。
3.清潔へのこだわり
風俗画は、清潔の概念を国家存立の基盤と見る社会をも映していた。オランダでは、近隣の清潔は住民たちの連帯の責任で保たれねばならず、不潔を許すことは一種の集団への裏切り行為であり、敵に門を開くに等しいと考えられていた。
逆に、清潔は、国の存立、道徳的意味合いを持っていた。新興の市民国家に生きるオランダ人にとって家庭こそが国の中心であった。全ての権威や道徳は家庭に生まれ、家庭に育まれる。とすれば、清潔が最も強く求められるのは家庭であり、家庭内で清潔を保つ仕事が女性の肩に掛かっていた。
4.17世紀のファッション・センス
17世紀半ば過ぎ頃にレンブラントが描いた肖像画を見ると、女性の身につけている衣装はほとんど黒いことに気づく。制作を求めたのは中流から上のクラスに属する人々。贅沢な服装が戒めや揶揄の対象とされるという伝統があったから、彩り華やかであったり、白く輝くサテンではなく、地味で目立たぬ服に身を包む方を意図的に選んだ。
スペインの支配下では黒の服が好まれたが、ミンスターの講和による最終的なスペイン支配の終焉とほぼ同じくして、色鮮やかな衣装とその豪奢なサテンの輝きが誇らかな自己顕示の形として選ばれた。中・上流の人々が好みの美しい衣装を楽しむ頃にフェルメールが風俗画を描き始めた。
5.手紙を読む女と書く女
17世紀初めに手紙が徐々に私的な情報のやりとりに使われるようになった。フェルメールの現存作品のうち、約5分の1にあたる6点は手紙をテーマとしている。
オランダの国教と定められたプロテスタントは、聖書を読むことの重要性を訴えた宗派である。信者は字を読む能力を備えていかなければならない。初等教育のための学校は、こうして教会との深い関連を保ちながら設立された。17世紀に5~14才までの65%は就学していた。識字率は、男で57%、女で32%。それでもオランダの女性の識字率は、他のヨーロッパ諸国に比べれば、驚くほど高い。男には書くことを、女には読むことを主として求めるという教育が施されていた。
C.プロフィール
フェルメールは17世紀オランダに活躍した風俗画家である。
1.画家への歩み
ヨハネス・フェルメールは、オラニエ家に縁の深いデルフトが豊かだった1632年に生まれた。当時父は、フォルデルスフラハトで2つの副業、織物業と画商を抱えての宿屋業だった。フェルメールの家として知られる「メーヘレン」に転居したのは、その10年後、1641年。
1653年末に聖ルカ組合に加入し、画家として独り立ちを果たす。自らの作品に署名を入れ、売却できるようになる。一人前の社会人としてスタートを切った。
当初、物語画家として出発したが、断腸の思いでその道を諦め、より多くの需要が期待できる風俗画に新天地を求めた。1660年代に入ってから、滑らかな仕上げ、穏やかな光、絵の具層の微妙な重ね具合、柔らかな輪郭線などの特徴を際立たせながら、傑作を制作し、独自の世界を創り上げることに成功した。
2.結婚とその後の暮らし
1652年に父が亡くなり、修行を急遽切り上げてデルフトに帰郷した。翌年の1653年4月、フェルメールは21才でカタリーナ・ボルネスと結婚した。1660年末にはマルクト広場近くの妻の実家に同居。隣に隠れ教会がある、かなり奥行きの深い家だった。アウエ・ランゲンデイク通りに面した2階建ての部分の後に、中二階の高さの建物、その背後に1階建ての低層部分が鰻の寝床のように続く構造。2階の通りに面した部屋にアトリエを構えていた。
フェルメールとその妻は23年の間に14人の子供をもうけ、そのうち10人(4人は乳幼児うちに亡くなる)をこの家で育てた。 義母とお手伝いさんを入れて大人4人、総勢14人が暮らすには、広い家とはいえ手狭だった。家の中には、子どもの泣き声や喚声など、生活音が耐えず賑やかに響いていた。
3.豊かな暮らし
当時の単純労働者の1日の賃金は1ギルダー弱、年間収入は200~300ギルダーほどと言われている。フェルメールが画家として活動するかたわら、画商を副業としていた。フェルメール一家の年間収入は夫婦会わせて800~1000ギルダー。自作の絵から400~600ギルダー、画商として200ギルダー、相続した債券の利息や家作の賃料などの不労所得300ギルダー。それなりに豊かさを享受していたが、大勢の育ち盛りの子供がいたので、年間200~300ギルダーを必要としていた。とはいえ、親の家に同居している彼らには家賃を払う必要がなかった。義母のマーリア・ティンスは、親族からの債券や土地、家作を相続し、およそ1500ギルダー以上の年収と2万6000ギルダーの財産があった。
①推定される制作の点数
現存作品は、33~36点と研究者により異なるが、筆者は32点を真作と見なしている。この他に、記録にのみ残る作品が10点、失われた作品が10点あったとすれば、フェルメールが制作した作品はおよそ55点になる。制作期間は聖ルカ組合に入った1653年から1675に没するまでの22年。年に2~3点というゆっくりとしたペースで仕事をしていた。構図を十分すぎるほどの緻密な計算の上に決定し、じっくりと時間をかけて狙った効果を追求する、それがフェルメールの画家としての日常だった。地塗りから最上層のグレージングに至るまで、極めて丁寧に用意周到に描き、細部も丁寧な仕上がりである。
ゆっくり丁寧に描き、しかも高価な青色顔料である天然ウルトラマリンを使い続けられたのは、強力なパトロンが存在したとする仮説もある。
ちなみにレンブラント(1606~1669)の制作期間は約45年。現存作品の数は、研究者により幅があるが、350点。 制作点数の1/4が伝わらなかったと仮定すると、推定される全制作点数は約470点。年に10点ほどのペースで仕事していた。レンブラントは、フェルメールとは異なり、莫大な家のローンを抱え、不労所得もなく、しかも浪費家であった。次々に作品を制作して、全ての支出を賄わなければならなかった生活の実情があった。
4.病気がちの晩年とその停滞の原因
1672年にフランス軍がオランダに侵攻して以来、オランダの経済は悪化の一途をたどる。そうした中で焦げ付き始めていた義母マーリアの必要に迫られた取り立てのため、フェルメールはアムステルダムなどへの遠出を繰り返すようになる。70年代のフェルメール作品の質は、制作に集中できない晩年の状況を反映し、驚くほど完成度が低い。
晩年の三作、《ギターを弾く女》、《信仰の寓意》、《ヴァージナルの前に座る女》の質の低下は、フランス軍の侵攻以来、美術市場が冷え込んだこと、義母の代理で貸し金の回収に走り回り、心静かにキャンヴァスに向かい微妙な細部の処理に腐心できる状態ではなかったことによるものだと説明できる。
5.没後の家族たち
1675年12月15日、フェルメール享年43才、早すぎる死。妻カタリーナは44才の若さにして10人の子どもを抱えた未亡人になった。10人の未成年の子どもを抱えた未亡人とその母にとって重要だったのは、今ある財産の目減りを少しでも抑え、幼い子どもたちの将来に備えることだった。装われた貧しさは2人の女の企み。カタリーナは時に生活に窮したが、いずれ相続する、債権者の手の届かぬ義母の財産の保全を図った。フェルメールの生前も没後も、一家は義母マーリアの家に住み、時に援助を受けながらそれなりの暮らしを楽しんでいた。
D.飽くなき洗練と絶え間なき自己変革
フェルメールは複雑な効果を色彩と形を通じて極めて単純に明快に提示している。その簡素さ、単純さ故に極めてストレートに見る者の心をつかんで離さない。
フェルメールは、単身像の風俗画に取り組み、生涯の終わりに至るまで繰り返し、その構図にこだわり続けた。その独特な構図によって、繊細さとニュアンスに溢れた光や色彩や空間が輝いている。
フェルメールは、自ら率先して試す画家というより、むしろ既存の型に学び、それを新しい型へじっくりと彫琢してゆくことに優れた画家だった。フェルメールにとっては、模倣は常に創造の始まりを意味する。
1.行為のない風俗画
フェルメールは、テル・ボルフが取り組んでいた風俗画から意味ありげな身振りや、物問いたげな視線といった、具体的な出来事を予測させるような要素を徹底して排除し、行為の伴わぬ風俗画という新しい画境を開いた。いかなる意味にも目的にも染まらずいる状態が最も端的に実現できる構図が単身だった。その構図は、色彩、光、形態といった造形的な問題に集中できた。
【レンブラントからフェルメールへ】
レンブラントの闇に輝く光を真昼間の白日の光に変え、洞窟のような空間を家庭の一室に移せば、フェルメールの作品が見えてくる。フェルメールは、レンブラントの作品から行為の欠如がもたらす「持続」の効果を学び、さらにそれを研ぎ澄まし、伝統的な図像の枠内でありながら、慣習的な意味の少ない風俗画の可能性を追求した。出来事の進行から解放された人物たちは、時間の狭間に潜む私的で内的な時間であって、現実の時を刻むことはない。絵画の中に生まれ、絵画の中に行き、絵画の中に回帰するしかない不思議な時間がそこにある。光の描写といい、室内の描写といい、いかにも写実性豊かなフェルメールの作品がどこか非現実的な雰囲気を漂わせているのは、独特の絵画的時間が流れていることが関連している。
2.風俗画第1作《取り持ち女》
1656年の年記を持つ《取り持ち女》が風俗画の第1作。他の風俗画に比べ、物語画的な香りを濃厚に放っていること、後に徐々にはっきりしてくる空間表現への関心がいまだ顕著でないことなど、過渡期の作品特有の特徴があまりに明らかだからである。
面白いのは、主題が物語から風俗に切り替わった時、フェルメールが描く様式もまた大きく変化させたこと。かつてのうねるような大胆な筆遣いはすっかり姿を消し、ほとんど筆触を残さぬ丁寧な塗りに変わってきている。
主題をカラヴァジストに求めつつも、描法に関しては小型の作品に適した当代の風俗画家を手本にしている。過渡的性格を窺わせるもう一つの特徴。
3.空間構成と人物配置
①空間表現
《眠る女》は、自らの描くべき風俗画の型をいまだ見出しきれなかった1650年代後半に制作。描写の重点があくまで前景にあり、構図の基本も前景にある。部屋の一隅に光を浴びる構図が既に姿を見せつつある。ただし、消失点の位置、窓の状態、椅子やテーブルの位置など情景には何かしらのぎこちなさが拭いきれずに残っている。空間の魅力を学んだが、首尾一貫した空間には至らなかった。空間の理論上のしつらえと目に映ずる像との間には、明らかに不自然なズレも認められる。しかし、その種の空間構成に関する関心が途絶えることなく持続していた。
【デ・ホーホとフェルメール】
2人の画家はほぼ同時にこの手の室内画の型に取り組んでいるが、先行したのはデルフトのもう一人の画家、ピーデル・デ・ホーホ(1629~1684)。彼が、1656年以降に矩形の室内空間を透視法的な正確さを愚直なまでに意識しつつ描き出すようになる。見た目に自然な空間ができあがるように、幾何学的遠近法を必要に応じて適当に調整する術を心得ていた。
これに対しフェルメールは、あくまで透視法の原則を遵守し、空間表現と登場人物の関係を極めて綿密に計算している。
②半身構図風俗画
《眠る女》の試みは、矛盾のもとになった前景重視と後景の抱き合わせを諦め、どちらかを捨てる決断をフェルメールに迫った。この後、再び後景を遮断した構図にかえっていく。構図と空間の2つを自然な関係に追求・融合させた明快で、しかも深みのある空間を前景を中心に展開していく。1660年代の傑作の明快きわまりない空間は、1650年代後半の試行錯誤の賜物。
テル・ボルフらカラヴァジストの構図には、最前景へモティーフを配置する試みが見事に取り入れられている。当代風の新基軸の風俗画であり、フェルメールが探し求めていた風俗画の型がそこにあった。
《窓辺で手紙を読む女》のすっきりした構図にやすやすと辿り着いたわけではない。X線写真を見ると、キューピッドの絵を塗りつぶし、レーマー杯の前にカーテンを下げ、構図から煩雑さを取り去ったことが判明する。事物を隠し、空間の深みを効率的に示唆するカーテンは秀抜のアイディアだった。
③近景に立つ単身の女性
フェルメールの風俗画の定型の一つ、最前景を占める単身増の風俗画は、《牛乳を注ぐ女》に至って完成する。《窓辺で手紙を読む女》に比べて3分の2ほどに縮まった画面には、カーテンも上下2段の窓もない。ここでも、透視法の効果を空間の演出に利用することを忘れていない。 女性の前の机だけは透視法から敢えて逸脱することにしたこと興味深い。厳格な透視法に執着したフェルメールが、近景造形と目に自然な空間の構成との調和を求めていきついた苦心の解決。
テル・ボルフを出発点とした単身の風俗画は、透視法、色彩、光の清新な効果を伴って、今やフェルメール独特の世界へと生まれ変わった。《取り持ち女》からわずか数年。その自己変革の驚異的な素早さは、若きフェルメールの貪欲なまでの模倣の精神と、豊かな創造的エネルギーとを何よりも雄弁に語っている。
4.初期風俗画の描法上の特徴
①透過する絵の具層と輪郭の処理
1650年代の《眠る女》では、女の顔に線と言えるような部分はほとんどない。 各モチーフの境界となる輪郭は、いずれも描かれるのではなく、示唆されるに留まっている。女の顔に無限のニュアンスを与えているのは、粘り気の強い絵の具をつけた筆がキャンバスの上を擦過してできた、所々に透けて見える下塗りの層。この層が上に置かれた絵の具のそこかしこに見え隠れしながら、人肌の複雑な色合い、顔の凹凸を演出する上で絶大な効果を発揮している。
1660年代に入って、下層の色彩を透過させ、表面の固有色に豊かな陰影を与える描法が顕著になる。表層の色彩の輝きや沈み具合、さらには各モティーフ、構図全体の明暗の案配は、下塗りの段階から既に計算されている。
【フアブリツィウスとフェルメール】の共通点は、壁や床の描き方
下塗りの層を巧みに透過させ、質感や彫塑感を示唆するこうした彩色法は、1650年ころからデルフトに住んでいたカーレル・フアブリツィウス(1622~1654、レンブラントの弟子)を強く想起させる。形態をかたどるきっちりとした線はどこにもない。下塗りの層の褐色は顔の赤みを演出し、表情を豊かなものにしている。
フアブリツィウスのゴキヒワ(マウリッツハイス美術館ルーム14に所蔵)
ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%82%B7%E3%82%AD%E3%83%92%E3%83%AF_(%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A6%E3%82%B9)
フェルメールは、空間描写ばかりではなく描法においても周囲の画家から学びつつ独自の様式の発見へと歩んでいった。空間構成とは異なり、学んだ描法をすぐさま変化させ、フェルメールの初期に独特のものへと鍛え上げていった。この変化と1658年頃から、鈍く輝く光を捨て、強く明るい外光の効果に関心を持ち始めたこととは無縁ではない。
②光の描写、質感の描写
《眠る女》の1~2年後に描かれたとされる《兵士と笑う女》は外の光が強さを失うことなく侵入してくる部屋の情景を描いた。強い光の下では陰影が青みを帯びるという、日常の繊細な光の観察のみが教えてくれる視覚現象をさりげなく、しかし大胆に視覚化されている。女性が被る頭巾の影の部分に添えられた薄い青。強い光が当たるところでは、窓の桟や士官の左肩が示すように、色彩が失われ、ただ白く輝くばかりという事実に気づかされるのも、この絵あたりから。
視覚現象をただただ描きとっただけではなく、絵画的工夫を通じて写実の効果をさらに高めることも忘れてはいない。彩色層の凹凸による光と影。明暗に従い、塗りの厚みに極端な変化をつけた。光のまぶしくあたる額や鼻筋などに白色系の顔料を盛り上げてハイライトとし、頭巾の影の部分は極めて薄い塗りで済ませる。見るものの視線は光に圧倒されて押し返され、影に引き込まれては画面の奥深くに入っていく。
色遣いもまた空間に深みを与える重要な手立てになっている。
光の滴のような点描法は、《窓辺で手紙を読む女》では控えめで目立たなかったが、《牛乳を注ぐ女》になると徐々に大胆さを増し、《デフルト眺望》では、実際の現象を離れて奔放に弾け画面を活気づけてゆく。
点描法は、光を一点に集め、強く反射する鋲や真珠などの素材では、かつてのような濃厚な点描が用いられることもあったが、フェルメール作品のごくごく控えめな点描は、1660年代に入ってからの特徴。こうした変化は、部屋に差し込む光がかつてほど強烈ではなくなったことも大いに関係する。穏やかな光は光の届かぬ部分から色彩を奪わず、対象を色調の無限の変化で包んでいく。光は、色彩と馴染み、色彩を内側から輝かせている。
《牛乳を注ぐ女》では、色彩にも新たな試みが認められる。光を浴びた前半身の背後の壁は暗く、影になった背中の後の壁は明るくといった具合に、明暗を巧みに操作し、人物の姿がくっきりと浮かび上がるように工夫している。
5.完成したフェルメールの世界
1660年代にはいると、風俗画の領域で独創性にあふれた極めて完成度の高い作品を制作し始める。見る者が写実的と見なしている特性でさえ、フェルメールの人の目を欺く操作であって、単なる写実の装いにすぎない。
1650年代の作品の特徴である顕著な厚塗り、赤・黄の暖色系を中心とした色調、透視法と視覚効果との間にいささかの乖離を感じさせる空間構成など、濃厚でやや強引な処理は姿を消し、代わって深みのある、くっきりと澄んだ世界が開けてくる。色彩は抑制の効いた青と黄が主役になり、涼しさを漂わせる。奥行きや消失点の位置などを計りに計って構想された空間は、近景主体であるにもかかわらず、かつてのような視覚的な無理を微塵も感じさせない。人物、机、椅子等々の数少ないモティーフが並ぶ部屋の中へ見る者は自然に誘い込まれ、静寂のひと時を描かれた人物と共に経験し、心ゆくまで堪能する。
①フェルメールの描いた部屋
フェルメール作品の空間の構成は、視覚的に極めて明快な印象を与える。
空間を仕切る奥の壁、左側の窓、大理石タイルの床、机と椅子、壁に掛けられた地図や絵などのモティーフは、空間を前後に直進し、真横に横切り、斜行し、画面の中に本物の部屋の一隅がまさしく現出したかのような錯覚を与える。こうした印象は、この空間が極めて合理的に構築されていること、それ以上に人物を含めた各モティーフの配置に工夫が凝らされていることから生まれる。実際にはごく狭い部屋の一隅が舞台になっているにもかかわらず、深みのある空間が自然にゆったりと人物を取り囲み、広がっているように見える。
②超前景の導入
1650年代のフェルメールは、幾何学的な透視法の原理と視覚印象とを融合させるため、《窓辺で手紙を読む女》ではカーテンを用い、《牛乳を注ぐ女》では机の形を変形させたりしていたが、1660年代には、一部しか描かれず、位置があいまいになったモティーフを巧みに配置して透視法が支配する空間と視覚印象に委ねられた「超前景」という具合に、それぞれがカヴァーする領域を巧妙に分離し、構図上の不自然さを解消させた。
モティーフの一部だけを断片で描くという処理は、フェルメールの独創ではないが、その処理を透視法的に構成された室内空間と結びつけて導入したのはフェルメールが初めてである。1650年代の試みの後に近景と遠景の抱き合わせが難しいことを知ったフェルメールは、遠景を断念し、代わりに透視法の枠に縛られない「超前景」を前景のさらに前方に重ねて、見た目に無理のない、しかし深々とした奥行きを備えた近景の造形に至りついた。
③フェルメールの作図法
フェルメールは、地塗りの済んだ画面の消失点のところにピンを刺した小さな欠損が見られるから、透視法の原理に精通していた。消失点の高さは視点の高さに、消失点と左右の遠隔点との間の距離は画面から視点までの距離に相当する。
フェルメールの考え抜いた技法を解説
vermeerpaint.com/210.html
フェルメールも、消失点・消失線、遠隔点・対交線に基づいた空間構成法を最初から縦横に使いこなせたわけではない。透視法に習熟するにつれて歪みや不自然さに気づき、次第に消失点を低めに、消失点と遠隔点との距離を大きめに、つまり画面から視点への距離を大きめにとり、視野角度を狭めるようになっていった。制作年代が後になるにつれ、34度、30度、22度と減少していっている。透視法が提示する空間は、晩年に近づくにつれて、見た目に歪みを感じさせなくなる。しかも、視点から画面までの距離は、「超前景」を導入することによって、実際より遙かに小さく感じられるようになっている。
④とびきり珍しい透視法作品
フェルメール作品では、正面奥の壁から視点までの距離はほぼ一定に保たれている。視点から奥の壁までの距離が一定の部屋を予め想定し、そこから逆算して消失点、遠隔点が定められている。
描くべき部屋よりも小さめの下絵を制作し、消失点、遠隔点を定め、その後それを拡大してキャンヴァスに写し取った。 フェルメールの空間は、緻密な計算に裏付けられて構成された「つくりもの空間」。
E.デルフトの街
フェルメールが生涯のほとんどを過ごしたデルフトは、中世の佇まいを偲ばせるレンガ造りの古い街並み、街を流れるいく筋もの小さな運河、その運河を跨ぐかわいらしい橋。かつては街の周りを巡っていた堅固な市壁は19世紀になって取り壊されて今はその姿を見ることはできないが、市壁の外側に水を湛えていた大きな運河のほとんどは現在も周辺の風景を映し出している。東西が800m、南北が1300mほどの小さな街は、その美しさ故にオランダの都市の中の真珠と謳われた。
1.デルフトとオラニエ家
16世紀、ネーデルランド(北部に現在のオランダ、南部にベルギー)の人々は、その地域の宗主権を握るハプスブルグ家スペインとの葛藤に苦しんでいた。プロテスタントを信仰する人々への弾圧、さらには経済的な収奪が世紀が進むに従い苛酷の度を強めていった。特に、カトリックの信仰を護持しようとするスペインが、6000あるいは8000人ともいわれる人々を断首した。こうした状況下にあって、1568年、反抗の狼煙を上げ、長い長い80年戦争の始まり。この時、諸州をまとめ陣頭に立って指揮をとったのが、オランダ建国の父と呼ばれるオラニエ家のウィレム沈黙公であった。彼は、1572年6月に拠点としていたハーグを捨てデルフトに住まいを移す決意をする。1584年、彼がスペイン放った刺客の手にかかり暗殺されたのも、デルフトだった。息子のマウリッツがスペインの無敵艦隊を倒し、オランダの実質的独立を果たすわずか4年前にこの惨劇は起きた。後を継いだマウリッツ公とフレデリック・ヘンドリック公が居所に選んだのは、デルフトではなくハーグだったが、オラニエ家の墓所はデルフトの新教会と定められている。デルフトは国家的な意味合いをうちに抱える街となった。
2.デルフトの経済繁栄
デルフトは、14世紀末に掘削を許されたスヒー運河を利用すれば、短時間に海上に出られる。先ずは海運業が発展し、醸造業、毛織物業、陶業などの発展を促すきっかけとなった。
17世紀に西インド会社、東インド会社も置かれた。スヒー港の南端に位置する、街の西側に流れるアウエ・デルフト運河沿いには、当時の豊かさを彷彿とさせる壮麗な建造物が今も往事の姿を偲ばせつつ軒を連ねている。富裕層の人々が住まう地域であった。
17世紀まで経済繁栄は続いたが、徐々に陰りを見せ始めた。東・西インド会社の主流がロッテルダムに奪われた。17世紀半ばの人口が2万人だったが、18世紀半ばには1万4千人にまで減少した。
- カテゴリー
- 世界の歴史観

