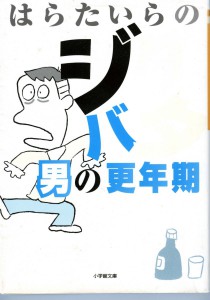本の世界
本の世界
2022年05月27日(金)
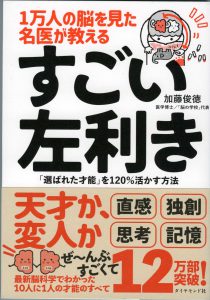 1万人の脳を見た名医が教える
1万人の脳を見た名医が教える
-「選ばれた才能」を120%活かす方法
著者 加藤俊徳
発行所 ダイヤモンド社
1430円
2021年9月28日 発行
左利きはアイデア出しや、ブレインストーミングなどは得意だが、思いついたことを具現化するのが得意な右利きの助けが必要となる。
左利きと右利きは、役割分担をすることで、左利きの持つアイデアを実施する確率がぐんと高まり、一方で右利きも、自分たちだけでは思いもよらない斬新なアイデアを取り入れることができる。 続きを読む
2017年11月04日(土)
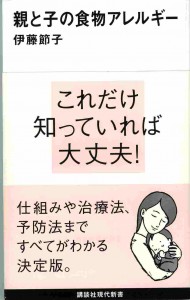 伊藤節子著
伊藤節子著
researchmap.jp/read0068981/
講談社現代新書
760円
2012年8月20日発行
略歴
1975年京都大学医学部卒業、武田総合病院小児科部長を経て、
2000年同志社女子大学生活科学部食物栄養科学教授科
「食べること」を目指した食事療法の研究をしている
食物アレルギーはアレルギー体質があることを示す最初の重要なサイン。乳児期発症の食物アレルギーの関与するアトピー性皮膚炎を正しく診断して治療することが大切。治療のゴールは、症状をおこさずに「食べること」と、気管支喘息を発症しないこと。 続きを読む
2016年03月11日(金)
 ANAビジネスソリューション講師 田口昭彦著
ANAビジネスソリューション講師 田口昭彦著
扶桑社
2015年9月1日発行
760円
「人的リソース」とは、人が持っている経験や知識、意見や情報、気づきのこと。この人的リソースを共有するために必要なのが「雑談」であり、その場が「雑談の場」である。雑談は「暗黙知」の宝庫。そして人と人との「関係の質」を高める「場」でもある。多種多様な職種の人間が一体感を持って、チームの目的を達成していくためには、雑談が必要。今は必要のない情報でも、いつかは必要になることが多々ある。
この本は、チーム作りや人財育成、そしてヒューマンエラーによるトラブル減少の役に立つと思う。 続きを読む
2008年09月21日(日)
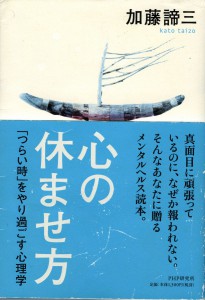 「つらい時」をやり過ごす心理学
「つらい時」をやり過ごす心理学
加藤諦三著
PHP研究所
2003年10月17日発行
「生きることに疲れた」人の気持ちがわかる一冊。この本を読むと、いろんな人がいることが理解できる。誰にでもプラスの発想を押しつけていたことを反省したい。 続きを読む
2023年08月28日(月)
 小児精神科医、社会を診る
小児精神科医、社会を診る
SNSの炎上、社会の分断への処方箋
著者 内田 舞 ハーバード大学准教授、脳科学者、3児の母
文春新書
2023年4月20日発行
1020円
A.子どもから学ぶアメリカ社会
1.親と子どもは独立した個人
アメリカでは、日常生活のあらゆる場面で、親と子どもが独立した個人であるという認識がある。子どもが親と違う意見を持った時にも、子どもの意見は子どもの意見として一旦受け止め、もし結果的に子どもの選択がよくない方向に向かっても、失敗に自身で対応することも子どもの人生の一部だと考える親も多い。また、最終的に親の意見を子どもに聞き入れてもらう場合であっても、どうしてそのような意見を持つのか親子の間で話し合う姿勢が中心にある。 続きを読む
2008年08月14日(木)
 蓮実香佑 著
蓮実香佑 著
PHP研究所
1300円
2005年11月9日発行
植物とは不思議な生き物である。人間とは姿も形もまったく違う。もっと根本的に考えも及ばない何かがあるのだと思う。手足も、目や耳も、脳もない。しかし、戦略家である。
また、余計なことを考えない植物のまっすぐな生き方に、私たちは「生きる」ことの意味を問い正されるかもしれない。
植物の不思議な世界へようこそ。 続きを読む
2008年09月13日(土)
悩める中年男性に大きな福音をもたらす告白書である。「トンネルには必ず出口がある」が心に残った。そして、「その時」がやって来たときにも、快適に乗り切るヒントがつかめると思う。不定愁訴を中心とした臨床症状に悩む男性がかなりの数に見られることが次第に明らかになってきている。つい最近までは、一般の人ばかりでなく、医学界でも”男性に更年期障害などあり得ない”という声が強かった。また、女性には「47歳の私に起こったこと」を読んでいただきたい。 続きを読む
2023年02月14日(火)
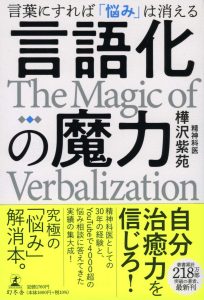 言葉にすれば「悩み」は消える
言葉にすれば「悩み」は消える
樺沢紫苑 著
幻冬舎
2022年11月10日発行
1600円
究極の「悩み」解消本、精神科医としての30年の経験とYouTubeで4000超の悩み相談に答えた実績の集大成。
精神医学の世界では、科学的根拠に基づいて医療を行う「エビデンス・ベイスト・メデイスン」に対して、患者の言葉、物語にもっと耳を傾けようという「ナラテイブ・ベイスト・メデイスン」が、昨今、注目を集めている。今の時代は、「エビデンス」よりも「ナラティブ(語り)」のほうが、人の心に響く。 続きを読む
2023年08月15日(火)
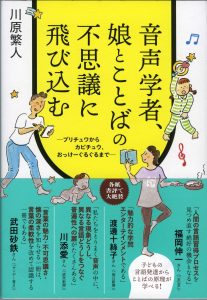 -プリチャアからピカチュウ、おっけーぐるぐるまで-
-プリチャアからピカチュウ、おっけーぐるぐるまで-
著者 川原繁人 専門は言語学、とくに音声学を研究
朝日出版社
2022年5月31日発行
1750円
言語学は、人間が発する「音声」を研究対象とする。どのように舌や唇を動かして声を発するのか、その声はどのようにして聞き手の耳に届くのか、聞き手はその音をどのように解釈するのか、これらのメカニズムを解き明かすことが音声学者の使命。
サポートページ
la-kentei.com/support/
user.keio.ac.jp/~kawahara/asahi.html 続きを読む
2025年02月02日(日)
 石井光太著
石井光太著
2024年7月20日発行
1700円
保育園から大学まで200人を超える教育関係者、保育園から高校の教員が30~50人くらいずつ、大学が15人ほど、年齢層は40代以上のベテランが7割、20~30代の若手も3割、にインタビューやアンケートから見えてきた、衝撃的な子どもたちの実態、保育園の4歳児の給食にミキサー食が提供されていることや昼寝に寝かしつけアプリが使われていること、幼稚園の運動会が中止になっていること、大人ファースト社会が子どもをスマホやゲームへ追い込むこと、スマホ育児により“養育者との心理的な結び付きの基盤が弱まり、発達が妨げられる”ことを、一部の出来事とするのか、近未来の前兆として捉えるかの選択を迫られている。 続きを読む