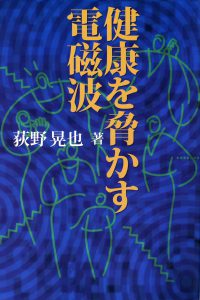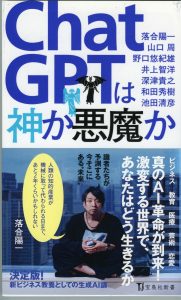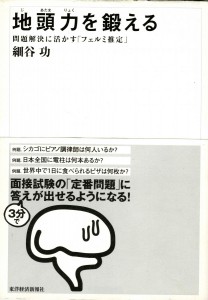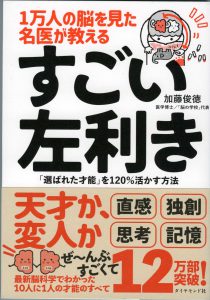センス・オブ・ワンダーを捜して
2011年12月08日(木)
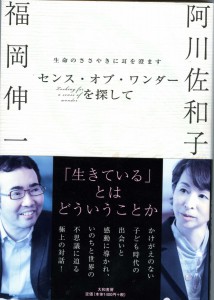 生命のささやきに耳を澄ます
生命のささやきに耳を澄ます
福岡伸一 阿川佐和子著
大和書房
2011年11月1日発行
1400円
人間にとって子ども時代とは、生きるとは何なのかを深く考えさせられる1冊である。そして、機械論的にこだわらず動的平衡も視野に入れて患者さんと向き合いたいと思う。
また、2人の対談からインタビューの秘訣も学んだ。質問をひとつだけ用意する。その答えをじっくり聞き、答えの中に次の質問を見つける。
生物と無生物のあいだ
kojima-dental-office.net/blog/20200914-14306#more-14306
動的平衡
kojima-dental-office.net/blog/20180814-10323#more-10323 続きを読む
クール・ジャパン!?
2024年07月23日(火)
 外国人が見たニッポン
外国人が見たニッポン
著者 鴻上尚史
講談社現代新書
2015年4月20日発行
900円
番組では毎回テーマを決めて8人の外国人と一緒に話し合う。タレントではなく、学生や仕事で日本に来たり、夫と共に赴任した人たち。
相手を知り、自分の国のことを具体的に知ることは、やがて、自分自身を知ることにつながる。世界にはこんな見方があり、こんな考えがある。多様であることを楽しむことは、きっと自分自身の人生も豊かにし、深くすることになる。 続きを読む
健康を脅かす電磁波
2021年10月27日(水)
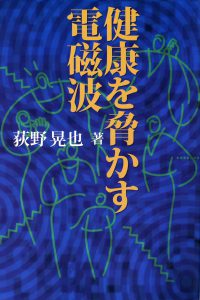 荻野晃也著
荻野晃也著
2007年5月10日発行
緑風出版
1800円
20年ほど前から送電線・変電所・配電線などの電力施設や家庭の電気製品などから漏洩してくる交流の低周波電磁波が、私たちの健康に悪い影響を与えるのではないかと言われ始めた。電磁波による影響には、白血病・脳腫瘍・乳ガン・肺ガン・アルツハイマー病が報告され、ノイローゼや自殺も関係があるといわれている。電磁波の健康への悪影響が完全に確定したわけではない。しかし、欧米では、「危険な可能性が高いのなら慎重に回避しようではないか」という「慎重なる回避思想」「予防原則思想」が広まっている。スウェーデン政府は、国レベルで「悪影響がある」と判断し、1992年末から具体的な対策を取り始めている。スイスやイタリアでは厳しい基準値を作り始めた。イギリスでは、16才未満には携帯電話を使わせないようにしている。 続きを読む
Chat GPTは神か悪魔か
2025年04月04日(金)
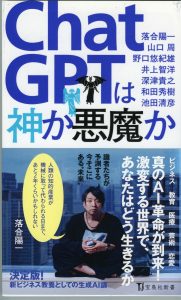 著者 メディアアーティストの落合陽一
著者 メディアアーティストの落合陽一
著作家・パブリックスピーカーの山口周
経済学者の野口悠紀雄
経済学者・駒澤大学経済学部準教授の井上智洋
インタラクション・デザイナーの深津貴之
精神科医・立命館大学生命科学部特認教授の和田秀樹
生命学者・早稲田大学名誉教授の池田清彦
宝島新書
1100円
2023年10月11日発行
本書では、各分野を代表する7名の識者が徹底検証する。
ChatGPTの操作はとても簡単で、誰でも直感的に使うことができる。時代に取り残されないためには「新しいものに触れる」という興味関心と行動力が大切。使い方はアプリをダウンロードして、質問を打ち込むだけ。できれば有料版で試してみよう。質問の仕方を工夫することで、より具体的かつ望ましい回答に近づけることができる。 続きを読む
地頭力を鍛える
2009年01月01日(木)
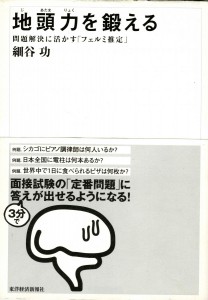 問題解決に活かす「フェルミ推定」
問題解決に活かす「フェルミ推定」
細谷 功著
東洋経済新報社
2007年12月20日発行
1600円
「日本全国に電柱は何本あるか?」
コピペ族が氾濫し、考える能力がますます退化していく現代において、人材確保のために利用している企業の面接問題である。考える手がかりもほとんど無い状況下で、3分以内に答えを出す。結果の正確さではなく、思考のプロセスを試す問題である。
また、「フェルミ推定」を使って地頭力を鍛えよう。自分なりに答えを出してページをめくり、答えを読むWhy型の好奇心を持ってこの本にチャレンジしていただきたい。 続きを読む
能登 海舟
2022年04月27日(水)
 www.hotespa.net/resort/hotellist/noto_kaisyu/
www.hotespa.net/resort/hotellist/noto_kaisyu/
25日(月)朝9時過ぎ青空広がる春、のと里山海道を北上。新緑に山桜が映える。藤の花もちらほら。気持ちよいドライブ。別所岳サービスエリアにて休憩をはさみ輪島へ。朝市の馴染み「手作りの店 すずき」にて、離乳期のスプーンを再びお買い上げ。お気に入りの「寿司処 伸福」にて地物にぎり、大満足。
今夜のお宿は、和倉温泉「白鷺の湯 能登 海舟」。函館で泊まったラビスタ函館ベイと同じグループ、共立リゾート。豪華な朝バイキング、いくら・帆立・イカの山盛りを思い出す。
食事処のおもてなし、大浴場や露天風呂の趣向、客室のしつらえに力を注ぎ込んでいる。ふんだんに使われる組み木、廊下全ての畳敷き。純和風でありながら、名湯をスマートな都会風に仕上げている。各部屋に海を見ながら入れる檜造りの天然温泉露天風呂とテラスを配置した斬新な設計、そして、豪華でモダンなベッドルールと寛ぎスペース。大浴場で疲れを癒やし、露天風呂で非日常を味わい、のんびり本を読み、1日を過ごす。海を見ながらゆったりと食事も最高だった。 続きを読む
すごい左利き
2022年05月27日(金)
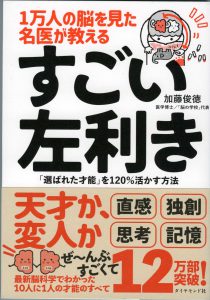 1万人の脳を見た名医が教える
1万人の脳を見た名医が教える
-「選ばれた才能」を120%活かす方法
著者 加藤俊徳
発行所 ダイヤモンド社
1430円
2021年9月28日 発行
左利きはアイデア出しや、ブレインストーミングなどは得意だが、思いついたことを具現化するのが得意な右利きの助けが必要となる。
左利きと右利きは、役割分担をすることで、左利きの持つアイデアを実施する確率がぐんと高まり、一方で右利きも、自分たちだけでは思いもよらない斬新なアイデアを取り入れることができる。 続きを読む
うなぎ川義
2021年02月06日(土)
 tabelog.com/ishikawa/A1701/A170102/17003753/
tabelog.com/ishikawa/A1701/A170102/17003753/
6日(土)夕方、宇ノ気の川義へ。たこのから揚げ、うなぎのホネ、きも焼き、うな重。ほっと一息。 続きを読む
宇野のり子 一人展とうなぎの浜松
2011年04月24日(日)
 宇野さんからのお便りに誘われて24日(日)に個展に立ち寄る。丹精込めた作品に囲まれて暖かい幸せな時間を過ごした。バックや額に人柄を感じるが、それに負けずにキャンバスの中でいろんな花が楽しそうに咲いていた。スイートピーの優しい水彩を1枚予約してきた。風に吹かれたつるに心惹かれる。これで2枚になる。
宇野さんからのお便りに誘われて24日(日)に個展に立ち寄る。丹精込めた作品に囲まれて暖かい幸せな時間を過ごした。バックや額に人柄を感じるが、それに負けずにキャンバスの中でいろんな花が楽しそうに咲いていた。スイートピーの優しい水彩を1枚予約してきた。風に吹かれたつるに心惹かれる。これで2枚になる。
水彩画 宇野のり子 風に吹かれて 続きを読む
金沢城と香林坊
2010年10月31日(日)
 10月31日(日)21世紀美術館へ北陸中日美術展を観に行った。久しぶりに金沢城まで足を伸ばした。中央公園脇の街路樹は、陽当たりか、風通りの影響なのか数本だけ紅葉していた。いもり坂口から登っていく。広々とした中に五十間長屋や河北門が甦る。まだまだ整備が続く。しかし、学生の頃はこの辺りに金沢大学の学舎や図書館、運動場があったと思いを馳せる。
10月31日(日)21世紀美術館へ北陸中日美術展を観に行った。久しぶりに金沢城まで足を伸ばした。中央公園脇の街路樹は、陽当たりか、風通りの影響なのか数本だけ紅葉していた。いもり坂口から登っていく。広々とした中に五十間長屋や河北門が甦る。まだまだ整備が続く。しかし、学生の頃はこの辺りに金沢大学の学舎や図書館、運動場があったと思いを馳せる。
当時を振り返り、香林坊へ。大神宮前の広場で行われていた大道芸やその賑わいを思い出す。再開発前の「北国書林」の裏手にあった「よこ山食堂」は、109ビルに入っていたが、姿を消していた。アルバイト時代によく食べていたから残念だ。てんぷら音羽屋も店主の張り紙があり、昭和の香りがまた一つ消えた。カツ丼の「ぶんぷく」は健在だ。それでも、今日は8番ラーメンを食べたくなった。金沢駅地下の金龍で、座って食べている人の後ろで汗かいて待ってまで食べたラーメンも懐かしい。
現代と少し前を訪ねた五千歩の散策だった。 続きを読む
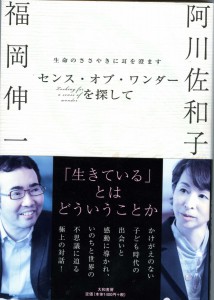 生命のささやきに耳を澄ます
生命のささやきに耳を澄ます