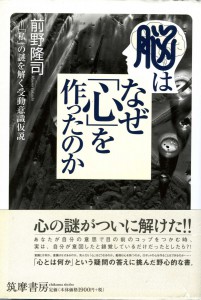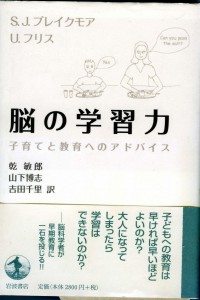医師や歯科医師の働き方改革
2022年07月19日(火)
2021年3月に「世界経済フォーラム」が、政治・経済・教育・健康の4項目で国内の男女格差を測る「ジェンダー・ギャップ指数」を発表した。日本は156カ国中120位であり、先進国では最下位、多くの新興国・途上国より低かった。政治分野で女性の進出が遅れていることが、日本の総合順位が低い最大の理由である。
ジェンダー・ギャップ指数2021
www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202105/202105_05.html
妊娠・出産は「生物学的性差」に基づいている。ただし育児は女性だけではなく、男性にもできる。社会には今なお「育児はママの仕事」という意識が根強く残っている。「男性でもできるのに、女性しかできないとされていること」、逆に「女性もできるのに、男性しかできないとされていること」、このような思いこみや決めつけが「ジェンダー・ギャップ」を生む。 続きを読む
国家の品格
2009年03月06日(金)
藤原 正彦著
新潮新書
2005年11月20日発行
680円
アメリカ化により、金銭至上主義に取り憑かれた日本人は、財力に任せた法律違反すれすれのメディア買収を、卑怯とも下品とも思わなくなってしまった。戦後、祖国への誇りや自信を失うように教育され、すっかり足腰の弱っていた日本人は、世界に誇るべき我が国古来の「情緒と形」をあっさり忘れ、欧米の「論理と合理」に身を売ってしまった。「国家の品格」をなくしてしまった。振れすぎた振り子を見直し、日本人の心を取り戻していただきたい。 続きを読む
壊れた脳 生存する知
2008年08月05日(火)
 著者 山田 規畝子
著者 山田 規畝子
発行 講談社
体裁 254頁・B6判
本体価格 1600円
発行 2004年2月26日
医師という病気を診るプロが、身をもって体験した自分の病気(認知障害)について書きとめた書である。三度の脳出血、その後遺症と闘う医師の生き方と「からっぽになった脳」を少しずつ埋めていく「成長のし直し」の記録である。自分の脳を、偉いなあ、と愛してあげて、一生懸命使ってくれる若者がひとりでも増えることを願っている。日ごろ診ている患者さんのいる世界かも知れないのに、想像したこともなかった。 続きを読む
ボッテガ ディ タカマッツォ
2017年04月14日(金)
 www.takamazzo.com/
www.takamazzo.com/
14日(金)窓辺から犀川の桜が見える片町のボッテガ ディ タカマッツォで北イタリアのトスカーナを楽しむ。素材そのものを活かした前菜、風味を際立たせたチーズの温前菜、海を感じる手長海老とアサリのパスタ、旨味をぎゅっと閉じこめた炭火焼きの牛と豚。どれも来れも力作揃い。幸せなひととき。 続きを読む
台風18号
2016年10月05日(水)
 www.asahi.com/articles/ASJB63S91JB6PJLB00B.html
www.asahi.com/articles/ASJB63S91JB6PJLB00B.html
5日(水)台風18号のため歯科部会は中止になった。夕方6時頃より風が吹き始め9時頃がピークだった。翌朝目が覚めると、裏の公園の大きな木が倒れていた。もう一本の同じ木は倒れなかった。風の流れの影響か。また、他の木に寄りかかり、教会は守られた。反対に倒れていたら、大惨事になるところだった。我が家は庭も畑も問題なかった。9時過ぎには伐採作業が始まり、夕方にはきれいに片づいていた。 続きを読む
脳はなぜ「心」を作ったのか
2008年08月11日(月)
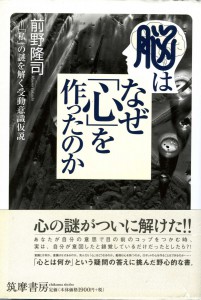 「私」の謎を解く受動意識仮説
「私」の謎を解く受動意識仮説
前野隆司著
筑摩書房
1900円
今で考えたこともない角度からの「心」について内容は、小びとたちを総動員、フル回転しても難解でした。皆さんも挑戦してみてください。
心は、小びとたちが織りなす巨大な連想ゲームの世界と、それを意識していると錯覚している「私」から成る。心を説明できるということは、死後の世界があり得ない。すべての喪失である死を明確な前提として生を考えなければならない。 続きを読む
新型コロナウイルス感染症の1年
2020年12月25日(金)
2月3日にダイヤモンド・プリンセス号が横浜港に着岸し、検疫を実施した。翌日、乗客にSARS-CoV-2 RNAが検出され、乗客、乗員全員が船内隔離された。乗員1,068人, 乗客2,645人の計3,713人が搭乗していた。その後4月15日までに確定症例712例が確認され, 少なくとも14例の死亡が、また, その他に検疫官や船会社の医師ら外部から対策に入った9人の感染も確認された。乗員の中では食事担当スタッフ(5.7%)は他スタッフ(0.7%)に比べ累積罹患率が有意に高かった。3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了した。新型コロナウイルスが国民的な関心事となったのは3月からだった。4月7日に緊急事態宣言が出された。 続きを読む
鈴木大拙館とホテルトラスティ金沢香林坊
2013年09月22日(日)
 www.kanazawa-museum.jp/daisetz/
www.kanazawa-museum.jp/daisetz/
9月22日(日)映画「風立ちぬ」鑑賞。山野草や雑草の忠実な描写にも感心する。その後、本多町の「鈴木大拙館」にて思索。また、その隣の「松風閣庭園」にて安らぎ。そして、今年6月にオープンしたホテルトラスティ金沢香林坊にて、非日常の昼食。鉄板の上を踊るニンニクの香りが脳を刺激する。ガーリックライスのお焦げ煎餅も美味しかった。 続きを読む
脳の学習力
2008年08月11日(月)
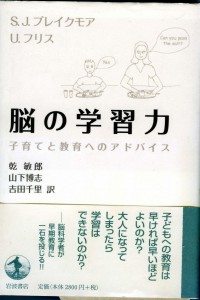 子育てと教育へのアドバイス
子育てと教育へのアドバイス
S.J.ブレイクモア、U.フリス 著
乾 敏郎、山下博志、吉田千里 訳
岩波書店
2800円
2006年10月17日発行
ここ数年、脳に関する本の出版が相次いでいる。しかし、現時点でわかっていないことや実証されていないことをここまではっきり書いている本は少ないと思う。教育者と脳科学者との交流がはじまり、最近の技術革新により脳の機能が明らかになり、脳と学習に関する研究がここまで進んでいる。医療、教育を始め、さまざまな分野の人々に読んでいただきたい1冊である。 続きを読む
マスコミ記者と意見交換
2019年07月18日(木)
 18日(木)石川県庁3階 県政記者室にて、「学校歯科健診後調査」に関して記者発表。マスコミ記者と概要内容について質疑応答後、今後の活動についても議論した。歯科健診で要受診とされたにもかかわらず歯科受診に至らない、さらには口腔崩壊にまでになる事例を踏まえて、全ての学校で周知・調査することを希望する。また、なぜそうなってしまうのかの原因を究明し、あらゆる対策を各分野の方々と連携・協力していきたい。すべての児童・生徒の口腔内ひいては全身や心の健康を願う。う蝕により噛めなくなると栄養バランスの偏り(食品多様性の欠如)がみられるようになる。特に、炭水化物(糖質)が過剰になり、タンパク質が低下する。将来、認知症や糖尿病も危惧される。
18日(木)石川県庁3階 県政記者室にて、「学校歯科健診後調査」に関して記者発表。マスコミ記者と概要内容について質疑応答後、今後の活動についても議論した。歯科健診で要受診とされたにもかかわらず歯科受診に至らない、さらには口腔崩壊にまでになる事例を踏まえて、全ての学校で周知・調査することを希望する。また、なぜそうなってしまうのかの原因を究明し、あらゆる対策を各分野の方々と連携・協力していきたい。すべての児童・生徒の口腔内ひいては全身や心の健康を願う。う蝕により噛めなくなると栄養バランスの偏り(食品多様性の欠如)がみられるようになる。特に、炭水化物(糖質)が過剰になり、タンパク質が低下する。将来、認知症や糖尿病も危惧される。
「よい歯のコンクール」だけではなく、こうした問題にも目を向け、今後も活動していきたい。 続きを読む