他職種連携
2016年11月02日(水)
 2日(水)石川県女性センターにて金沢在宅NST経口摂取相談会主催の研修会「誰でもできる嚥下食・キホンのキ」がありました。30数名の参加がありました。和気あいあいとした楽しい実習でした。エプロン姿も皆さん似合っていました。お茶のトロミ3段階(薄い、中間、濃い)の付け方を実習しました。そして、スクランブルエッグも各々作ってみました。出来上がりに個性がありました。実際に試食してみると、薄いトロミやゼリー茶の方が美味しかったです。利用者さんの食べ方、嚥下の状態などを診て基本を参考に付け方を工夫したいと思います。 続きを読む
2日(水)石川県女性センターにて金沢在宅NST経口摂取相談会主催の研修会「誰でもできる嚥下食・キホンのキ」がありました。30数名の参加がありました。和気あいあいとした楽しい実習でした。エプロン姿も皆さん似合っていました。お茶のトロミ3段階(薄い、中間、濃い)の付け方を実習しました。そして、スクランブルエッグも各々作ってみました。出来上がりに個性がありました。実際に試食してみると、薄いトロミやゼリー茶の方が美味しかったです。利用者さんの食べ方、嚥下の状態などを診て基本を参考に付け方を工夫したいと思います。 続きを読む
2008年10月02日(木)
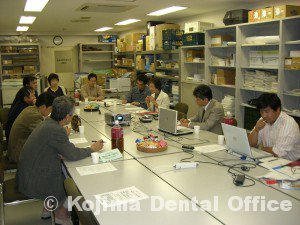 とき 2008年10月2日(木)19時~22時00分
とき 2008年10月2日(木)19時~22時00分
場所 保険医協会会議室
パネラー 不島先生、近藤先生、長門先生
内容 不島先生:「食性と顎発育」
長門先生:「口腔筋機能トレーナー等を使った症例について」
近藤先生:「最近の小児の口腔機能の変化と対策について」 続きを読む
2015年11月02日(月)
 金沢在宅NST経口摂取相談会
金沢在宅NST経口摂取相談会
第2回 サポーター限定研修会
研修内容 1.車椅子姿勢と調整方法について考えよう。
みんなで体験しよう(実技あり)
2.食事について(姿勢や感覚情報、手の使い方)、
もう一度考えよう
講 師 映寿会みらい病院 理学療法士 神野俊介
金沢西病院 作業療法士 白山武志
第2回 サポーター限定研修会 ポスター 続きを読む
2006年10月27日(金)
近藤政子、長門佐、小島の3人は、27日(金)に朝の飛行機で東京へ向かい、昭和大学歯科病院 歯科リハビリテーション科を訪問した。向井教授と医局員やスタッフの協力と患者さんや介助者のご理解のもと実際の治療を見学することができた。 続きを読む
2014年07月15日(火)
 講演と実技
講演と実技
14日(月)午後7時から金沢在宅NST経口摂取相談会主催のサポーター限定研修会「姿勢が変われば嚥下が変わる」がありました。50名ほどの参加があり、熱気を帯びた有意義な会でした。
5~10cmずり落ちた状態で背板をギャッジアップした苦しい状態と「背ぬき」・「足抜き」による楽になる体験。また、大腿部と前腕、足底のクッションによるサポートやひみこタオルを体験。 続きを読む
2013年02月16日(土)
 口腔機能維持管理体制加算 施設の口腔ケア・マネジメント計画書 介護老人保健施設 内灘温泉保養館が来月から口腔機能維持管理体制加算を算定したい旨の連絡を受けて、1/17(木)午後1時半~2時半にその打ち合わせにお伺いしました。口腔ケアを推進するための課題、目標、具体的方策、留意事項など入所者の口腔ケア・マネジメントに係わる計画について、そして、基礎講習会の開催日程、対象者、内容についても協議しました。また、訪問診療の曜日や時間帯も調整しました。
口腔機能維持管理体制加算 施設の口腔ケア・マネジメント計画書 介護老人保健施設 内灘温泉保養館が来月から口腔機能維持管理体制加算を算定したい旨の連絡を受けて、1/17(木)午後1時半~2時半にその打ち合わせにお伺いしました。口腔ケアを推進するための課題、目標、具体的方策、留意事項など入所者の口腔ケア・マネジメントに係わる計画について、そして、基礎講習会の開催日程、対象者、内容についても協議しました。また、訪問診療の曜日や時間帯も調整しました。
2月1日に、内灘温泉保養館と協力医院契約を結び、入所者の歯科に関しての診察、治療などの処置を図ることになり、また、施設の口腔機能維持管理体制も応援することになりました。 続きを読む
2018年10月28日(日)
25日(木)午後、保険医協会歯科理事4人で公立能登総合病院歯科口腔外科を訪問。診療部長の長谷先生に歯科衛生士と言語聴覚士による患者さんの事前評価と今回の目的を解説してもらい、2人の病室へ向かう。それぞれの担当看護師、管理栄養士を加えた5職種による摂食嚥下機能評価とVEの実際を見学した。病態から予想されることを頭に描きながら検査を進める。食形態やトロミ調整と姿勢や頸部回旋などによる嚥下機能の変化を確認する。煎餅やトロミ無しのお茶が飲めるのに、粥やペースト食を食べたがらない患者を嗜好との関連も考慮した上でつぶさに評価し、プロセスリードを用いて咀嚼や舌による押しつぶし機能を判断していた。現場からの要望に対しても即座に対応していた。トラブルのため服薬中止となった錠剤の飲み込みをVEで観察し、服薬ゼリーを提案していた。チームで考えられる問題点や対応策が導き出され、長谷先生が摂食嚥下担当医として報告書を作成していた。 続きを読む
2011年06月22日(水)
 講師 栗田 志麻 管理栄養士
講師 栗田 志麻 管理栄養士
日時 平成23年6月22日 午後5時30分~6時30分
場所 向粟崎保育所
対象 保育士、調理師
主催 内灘町保健センター 続きを読む
2025年09月10日(水)
 10日(水)13時半から内灘町保健センターにて食育推進会議。食育推進計画の進捗状況と現在や今後の取り組みについて事務局からパワーポイントデータを用いて説明があり、各委員、それぞれの立場、職種からの質問、提案があり有意義な会議となった。特に、能登半島地震以降、仮設住宅などにより遊び・運動できる広場の減少と、安全確保のための徒歩からスクールバスへの変更による運動機会の減少によって肥満傾向にある子どもの割合が増えていることが指摘された。そして、早寝早起きの基本的生活習慣の目標が、3歳児の脳を働かせるセロトニンをより多く分泌させる夜8時朝6時ではなく夜10時朝8時にせざるを得ない現代社会のひずみも気になる。子どもを考えた視点ではなく、大人ファースト。最後に3歳児の不正咬合が増えている現状と原因、対策について解説した。 続きを読む
10日(水)13時半から内灘町保健センターにて食育推進会議。食育推進計画の進捗状況と現在や今後の取り組みについて事務局からパワーポイントデータを用いて説明があり、各委員、それぞれの立場、職種からの質問、提案があり有意義な会議となった。特に、能登半島地震以降、仮設住宅などにより遊び・運動できる広場の減少と、安全確保のための徒歩からスクールバスへの変更による運動機会の減少によって肥満傾向にある子どもの割合が増えていることが指摘された。そして、早寝早起きの基本的生活習慣の目標が、3歳児の脳を働かせるセロトニンをより多く分泌させる夜8時朝6時ではなく夜10時朝8時にせざるを得ない現代社会のひずみも気になる。子どもを考えた視点ではなく、大人ファースト。最後に3歳児の不正咬合が増えている現状と原因、対策について解説した。 続きを読む
2013年02月02日(土)
 1月28日内灘温泉保養館事務より歯が痛い入居者がいるので診て欲しいとの連絡が入る。歯に大きな穴があいているなどの情報と全身疾患や内服薬、心身やADLの状況などを記入した調査票を入手する。河北歯科医師会から、ポータブルX線装置とポータブルユニットを借りる。 30日に訪問し、主訴と全身状態の確認後、口腔内診査と持参したポータブルX線装置による左上3,4番の撮影を行う。そして、治療計画の概要を本人、家族、担当看護師に説明する。電源と手洗いの位置を含めた、提供される診療場所の下見と実際に使用するリクライニング車椅子での治療体勢のシミュレーションを行う。帰院後、90分の治療時間を確保するために予約変更を行い、必要な機材、器具と薬剤の準備を整える。 続きを読む
1月28日内灘温泉保養館事務より歯が痛い入居者がいるので診て欲しいとの連絡が入る。歯に大きな穴があいているなどの情報と全身疾患や内服薬、心身やADLの状況などを記入した調査票を入手する。河北歯科医師会から、ポータブルX線装置とポータブルユニットを借りる。 30日に訪問し、主訴と全身状態の確認後、口腔内診査と持参したポータブルX線装置による左上3,4番の撮影を行う。そして、治療計画の概要を本人、家族、担当看護師に説明する。電源と手洗いの位置を含めた、提供される診療場所の下見と実際に使用するリクライニング車椅子での治療体勢のシミュレーションを行う。帰院後、90分の治療時間を確保するために予約変更を行い、必要な機材、器具と薬剤の準備を整える。 続きを読む

