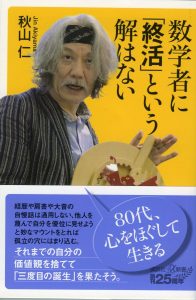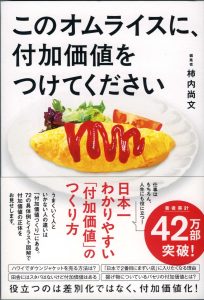宮古諸島5島 至高の休日4日間
2026年01月30日(金)
 25日(日)の朝、金沢60センチ以上、内灘町でも40センチ以上の積雪。8時に「正午から町の一斉除雪が始まるので車を道路に駐車しないように」との町内放送。自宅の玄関、医院の玄関や周りと患者さん用やスタッフの駐車場を老夫婦二人で、2時間ちょっと除雪した。小松空港でも羽田2便が欠航したので、旅行に行けるか心配した。
25日(日)の朝、金沢60センチ以上、内灘町でも40センチ以上の積雪。8時に「正午から町の一斉除雪が始まるので車を道路に駐車しないように」との町内放送。自宅の玄関、医院の玄関や周りと患者さん用やスタッフの駐車場を老夫婦二人で、2時間ちょっと除雪した。小松空港でも羽田2便が欠航したので、旅行に行けるか心配した。
27日(火)何とか雪国を脱出し、暖かな宮古島をのんびり楽しんだ。青い空、青い海も格別だった(写真は29日の渡口の浜)。2夜も島唄ライブを満喫した。 続きを読む
金城大学ダンス部第18回定期公演
2020年12月27日(日)
 27日(日)金城大学ダンス部は定期公演の無観客オンラインyutube配信に挑戦した。コロナ禍にあって様々な困難をOBOGなど多方面の協力を得て、チームワークと工夫で成功に導いた。さぞかし綿密な打ち合わせと事前準備に熱意を費やしたのだろう。遠近のカメラワークをダブらせる見事な演出を同時配信で成し遂げていた。台詞はマウスシールドを使い感染対策に注意を払っていた。ダンスミュージックと台詞との音量バランスには課題があった。
27日(日)金城大学ダンス部は定期公演の無観客オンラインyutube配信に挑戦した。コロナ禍にあって様々な困難をOBOGなど多方面の協力を得て、チームワークと工夫で成功に導いた。さぞかし綿密な打ち合わせと事前準備に熱意を費やしたのだろう。遠近のカメラワークをダブらせる見事な演出を同時配信で成し遂げていた。台詞はマウスシールドを使い感染対策に注意を払っていた。ダンスミュージックと台詞との音量バランスには課題があった。
逆境の中にあっても、キレキレのダンスに仕上げてきた。元気をもらえた。全国各地の自宅やグループでビデオ参加したOBOGのパフォーマンスは楽しかった。特にその二世たちのダンスが可愛かった。 続きを読む
金城大学ダンス部第17回定期公演
2020年01月05日(日)
 5日(日)午後、10年以上も通い続けている金城大学ダンス部定期公演へ。今年も去年と同じく正月開催。場所は野々市市文化会館フォルテへ変更になった。会場は超満員。幕が上がると同時にパワフルなキレキレのダンス。ビートがお腹に響き、アドレナリン全開。体中にエネルギーがみなぎり自然と体がリズムを刻む。息の揃ったパフォーマンスは絶好調。ハードな練習が目に浮かぶ。コンセプトに絆と一生懸命が感じられる。
5日(日)午後、10年以上も通い続けている金城大学ダンス部定期公演へ。今年も去年と同じく正月開催。場所は野々市市文化会館フォルテへ変更になった。会場は超満員。幕が上がると同時にパワフルなキレキレのダンス。ビートがお腹に響き、アドレナリン全開。体中にエネルギーがみなぎり自然と体がリズムを刻む。息の揃ったパフォーマンスは絶好調。ハードな練習が目に浮かぶ。コンセプトに絆と一生懸命が感じられる。
ストリーパートのテーマ選択もバッチリ。オリンピックからのパラリンピック。流行語が所々にちりばめられ面白かった。長ぜりふも完璧。車椅子ダンスも楽しかった。 続きを読む
金城大学ダンス部第16回定期公演
2019年01月06日(日)
 6日(日)午後、時々ちらちら小雪舞う寒い日に白山市松任文化会館へ。10年も通い続けている金城大学ダンス部定期公演。いつもは12月にあるのに、今回は正月。それもあるのか和風な感じ。部員数が少なくなって心配していたが、それを吹き飛ばす、ビートに乗ったパワフルなキレの良いダンスは健在。一致団結した、息の揃ったパフォーマンスも気持ちよかった。よほどの練習量だろう。優雅なバレーパートや力強いチアリーディングの要素も素晴らしかった。引き込まれるストーリーパートの展開が良かった。メリハリのある語り口は心に響いた。
6日(日)午後、時々ちらちら小雪舞う寒い日に白山市松任文化会館へ。10年も通い続けている金城大学ダンス部定期公演。いつもは12月にあるのに、今回は正月。それもあるのか和風な感じ。部員数が少なくなって心配していたが、それを吹き飛ばす、ビートに乗ったパワフルなキレの良いダンスは健在。一致団結した、息の揃ったパフォーマンスも気持ちよかった。よほどの練習量だろう。優雅なバレーパートや力強いチアリーディングの要素も素晴らしかった。引き込まれるストーリーパートの展開が良かった。メリハリのある語り口は心に響いた。
参考に
金城大学ダンス部創立20周年記念OBOG公演「DECADE×2.0」
kojima-dental-office.net/blog/20180930-10405 続きを読む
数学者に「終活」という解はない
2025年11月25日(火)
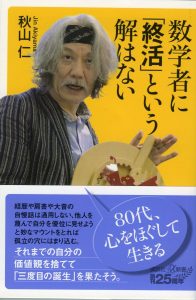 著者 秋山仁
著者 秋山仁
2025年10月7日 発行
講談社α新書
1100円
来年80才。神様がいつまで与えてくれるか分からない時間を自分で精一杯面白く、かつ温かいものにできるか、いくつになっても人生は挑戦だと思うこの頃。明治から昭和にかけて活躍した小説家の正宗白鳥は、「人生は知ることではなく、味わうもの」と言っている。終活といわれる類のものに人生の時間を使うことが、自分の人生にとってはベストな解だとは思えない。
みなさん、この世に生を受けた者同士、“人生最後に向けての過ごし方”という難問に自分自身のベストな解を見つけるべく、お互いに頑張りましょう。 続きを読む
励もう会in広島
2018年09月24日(月)
 30.9.22~24.
30.9.22~24.
大学時代の友人が集う年1回の夫婦同伴旅行会が今年は広島。幹事神野君の緻密な下調べと素晴らしい計画。初めて訪れる福山、懐かしい、癒される港町、鞆の浦。シンボル常夜燈に集う常連さんの優しさ。指示通りの立ち位置で完璧な一枚。対潮楼からの絶景。保命酒で栄えた中村吉兵衛の考え抜かれた建物と庭との空間的位置関係。
大学時代の広島
kojima-dental-office.net/blog/19750411-3080#more-3080 続きを読む
このオムライスに、付加価値をつけてください
2025年10月09日(木)
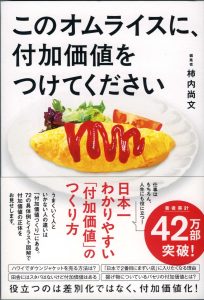 柿内尚文著
柿内尚文著
2025年2月27日発行
ポプラ社
1500円
付加価値をつくることができると、人生を豊かにおもしろく変えることができる。付加価値を知ることは、仕事にも、人生にも、大いに役立つ。何を優先すればいいか、何を目標にすればいいか、どんな行動をしたらいいかなど、人生や仕事の指針を作ることにもつながる。仕事を人生を、新たな視点で捉え直し、自分の強みを見つけ新しい一歩を踏み出そう。
仕事は「付加価値をつくる」ことと「作業する」ことに分けられるが、成果につながる付加価値をつくることが評価されやすい。作業する時間よりも付加価値をつくる時間を増やしていくことが、自分ならではの仕事をすることになる。 続きを読む
七尾食祭市場
2024年10月27日(日)
 www.shokusai.co.jp/
www.shokusai.co.jp/
27日(日)選挙を済ませ、金沢マラソンなので混雑を避けて、地震以来久しぶりに七尾へ。のと里山海道の徳田大津から能越自動車道に入ると、道路は修復されているが明らかにまだ波打っていた。道路脇の歩道は崩れて応急措置のみで修復は手つかずのままだった。食祭市場も震災の爪痕がかなり残り、仮復旧の状態で本格的な復興はまだまだの感じだった。七尾湾隆起の影響を受けなかったのか遊覧船は通常通り運航していた。飲食店は数店閉店していた。土日祝日のみ営業の特設浜焼きテントが盛況だった。カニ足・ホタテ・赤エビ・ サザエ・ハマグリ・イカ・ホッケの一夜干し、カニ汁や市場内のアジや鰤のにぎりも美味い。夕飯にブリ鎌とボタン海老。 続きを読む
金城大学ダンス部第15回定期公演
2017年12月24日(日)
 24日(日)暖かなイブ、先週は雪が積もっていたのに。石川県こまつ芸術劇場うららにて金城大学ダンス部第15回定期公演を鑑賞。超満員。毎年年末の恒例行事。もう10年も来ている。ビートに乗ったパワフルなキレの良いダンスがいつにも増して素晴らしかった。チアリーダーの要素も取り入れ、高さも新たに表現。優雅なバレーパートも綺麗だった。今年は部員数が減ったが、かえってその分細部まで行き届いていた。そして、創部以来初めての2年生部長を中心に団結力が見られた。また、振り付けや指導にOGOBのサポートが十二分に感じられた。ダンスミュージカルでは、山下清風など豊かな個性をそれぞれが演じきり光っていた。ストリーに目頭が熱くなる場面もあった。にゃんこスターの動きや荻野目洋子の踊りなど話題もしっかり取り入れていた。明るく元気な気分になり、楽しい一日だった。 続きを読む
24日(日)暖かなイブ、先週は雪が積もっていたのに。石川県こまつ芸術劇場うららにて金城大学ダンス部第15回定期公演を鑑賞。超満員。毎年年末の恒例行事。もう10年も来ている。ビートに乗ったパワフルなキレの良いダンスがいつにも増して素晴らしかった。チアリーダーの要素も取り入れ、高さも新たに表現。優雅なバレーパートも綺麗だった。今年は部員数が減ったが、かえってその分細部まで行き届いていた。そして、創部以来初めての2年生部長を中心に団結力が見られた。また、振り付けや指導にOGOBのサポートが十二分に感じられた。ダンスミュージカルでは、山下清風など豊かな個性をそれぞれが演じきり光っていた。ストリーに目頭が熱くなる場面もあった。にゃんこスターの動きや荻野目洋子の踊りなど話題もしっかり取り入れていた。明るく元気な気分になり、楽しい一日だった。 続きを読む
畑2022
2022年12月25日(日)
 今年は、漬物が美味い。畑の旬野菜とカンタン酢、ぬかチューブ、わさび漬けの素が大活躍。朝のお供に彩り。春のエシャロット、夏から秋のキュウリ、ナス、コリンキー、生姜、冬の源助大根と聖護院かぶ、ラディッシュ(二十日大根)、藤しぐれ(紫白の小カブ)。ケンミンSHOWで見た博多の居酒屋メニューのピーマン類“パリピー”もよかった。 続きを読む
今年は、漬物が美味い。畑の旬野菜とカンタン酢、ぬかチューブ、わさび漬けの素が大活躍。朝のお供に彩り。春のエシャロット、夏から秋のキュウリ、ナス、コリンキー、生姜、冬の源助大根と聖護院かぶ、ラディッシュ(二十日大根)、藤しぐれ(紫白の小カブ)。ケンミンSHOWで見た博多の居酒屋メニューのピーマン類“パリピー”もよかった。 続きを読む
 25日(日)の朝、金沢60センチ以上、内灘町でも40センチ以上の積雪。8時に「正午から町の一斉除雪が始まるので車を道路に駐車しないように」との町内放送。自宅の玄関、医院の玄関や周りと患者さん用やスタッフの駐車場を老夫婦二人で、2時間ちょっと除雪した。小松空港でも羽田2便が欠航したので、旅行に行けるか心配した。
25日(日)の朝、金沢60センチ以上、内灘町でも40センチ以上の積雪。8時に「正午から町の一斉除雪が始まるので車を道路に駐車しないように」との町内放送。自宅の玄関、医院の玄関や周りと患者さん用やスタッフの駐車場を老夫婦二人で、2時間ちょっと除雪した。小松空港でも羽田2便が欠航したので、旅行に行けるか心配した。