生物はなぜ死ぬのか
2022年02月27日(日)
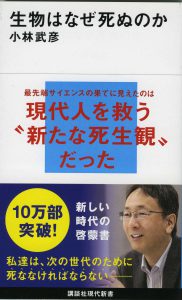 小林武彦著
小林武彦著
講談社現代新書
900円
2021年4月20日発行
遺伝子の変化(変異)が多様性を生み出し、その多様性があるからこそ、死や絶滅(選択)によって生物は進化してこられた。その過程で人類を含む様々な生き物は、様々な死に方を獲得してきた。現在も「細胞や個体の死」が存在し続けるということは、死ぬ個体が選択されてきたということ。「生き物が死ぬこと」も進化が作った。
老化というヒトに特有の現象は、どういう意味があるのか。ヒトの体内にわざわざ細胞を死なせるプログラムを遺伝子レベルでなぜ組み込んだのか。
A.そもそもヒトはどのように死ぬのか
体は、組織や器官が形成されていく過程で、構成する3種類の細胞に分かれる。組織や器官を構成する細胞(体細胞)、失われた細胞を供給する「幹細胞」そして、卵や精子を作る生殖系の細胞。
1.体細胞の老化
体が完成すると、後はひたすら古い細胞と新しい細胞の入れ替えを繰り返す。体細胞の中で心筋と神経細胞は例外的に入れ替えをしない。
①細胞は約50回分裂すると死ぬ
ヒトの体細胞は約50回分裂すると、老化して分裂をやめてしまい、やがて死ぬ。60年ほど前にアメリカのレオナルド・ヘイフリックという研究者が、組織からとりだしたヒトの細胞をペトリ皿で培養した時に見つけた現象。さらに興味深いのは高齢者から取り出した細胞は、分裂回数が50回よりも少なくなる。
②テロメアが細胞の老化スイッチをオンにする
細胞分裂のたびにヒトの体細胞のテロメアは短くなる。テロメアの長さが本来の長さの半分くらいになると、そこから信号が発せられ、細胞の老化スイッチがオンになる。このテロメアの短縮による老化の誘導が、ヘイフリックが見つけた細胞の分裂回数を制限するメカニズムの正体だった。
DNA合成(複製)の際に、端っこが複製できない。DNA合成酵素が複製を始める時には、まず相補的なプライマーと呼ばれる短いRNAが必要。合成できる方向が一方向のため、2本鎖のDNAを複製する場合に、一方の鎖を鋳型とした場合は染色体の末端まで合成できるが、反対の鎖を鋳型とした場合は素直に合成方向には進めない。そのため、DNA複製のたびにプライマーの分だけ短くなる(詳しくは原著138ページの図を参照)。 実際に、染色体の末端の繰り返し配列(テロメアという)の長さは、若いヒトのほうがシニアのヒトより多少長い。
③進化によって獲得された老化
細胞が老化して死なないと、古い細胞が溜まっていく。細胞内のミトコンドリアが酸素呼吸を行い、エネルギーを作り出す。この時に副産物として酸化力の強い「活性酸素」が生じる。これが、細胞成分(タンパク質、核酸、脂質)を酸化し、細胞の機能を低下させる。機能が低下した細胞の中には異常なものも現れる。一番困るのは、がん化。
細胞が分裂を繰り返すとゲノムに変異が蓄積し、そのうちに細胞増殖のコントロールに関わる遺伝子が壊れると、制御不能になってどんどん細胞が増殖し、がん化する。
細胞の老化には、活性酸素や変異の蓄積により異常になりそうな細胞を異常になる前にあらかじめ排除し、新しい細胞と入れ替えるという重要な働きがある。これによって、がん化のリスクを抑えている。テロメア合成酵素の働きをわざわざ止めてまで老化を誘導する。老化もまた、ヒトが長い歴史の中で「生きるために獲得してきたもの」と言える。
でも、ヒトの場合には55歳くらいから、がんによる死亡率が急激に上昇する。1981年以来、日本人の死因の1位はがん。「ゲノムの寿命は55歳」と言うこともできる。進化で獲得した想定(55歳)をはるかに超えて、ヒトは長生きになってしまった。
④細胞死を誘導するp53というタンパク質
組織の細胞を入れ替えるためには、新しい細胞の供給に加えて、老化した古い細胞の除去が必要。老化細胞の除去には、細胞自身の「アポトーシス」という細胞死と、免疫細胞による貪食がある。加齢した個体の老化細胞は除去が起こりにくく、そのまま組織内に留まる傾向がある。老化細胞が排除されないで残ると、組織を害し器官の機能を低下させる。
オランダのグループが2017年に発表した論文。細胞死を誘導するp53というタンパク質をFOXO4というタンパク質が阻害するから、マウスに加齢とともに老化細胞が溜まっていく。邪魔できないようにp53の結合部位にくっつく小さなタンパク質(ペプチド)を合成し、投与すると細胞死が誘導され、肝臓及び腎臓の機能が回復し、運動機能が向上し、さらには毛がふさふさ生えてきた。
加齢による老化現象は、排除されない老化細胞に一因がある。人でのこのペプチドの安全性、有効性は現在研究中。
2.幹細胞の老化
①テロメア合成酵素(テロメアーゼ)
幹細胞と生殖細胞は、テロメア合成酵素によって常に伸張されている。
ゾウリムシの仲間のテトラヒメナのテロメアは染色体が複製しても短くならない。アメリカの生物学者エリザベス・ブラックバーンらは、テトラヒメナのテロメアを用いて、テロメアを伸ばす働きを持つテロメア合成酵素(テロメアーゼ)を発見した。
②幹細胞も老化する
幹細胞といえども加齢とともにこの酵素の活性が低下し少しずつテロメアは短くなり、新しい細胞の供給は徐々に減っていく。一番影響が出るのは、新しい細胞を大量に必要とする血液や免疫細胞を作る造血幹細胞など。免疫に関わる細胞の生産が低下すると、感染した細胞や異常細胞の除去ができにくくなる。
また、幹細胞は、DNAに傷が付くことで老化が促され、結果として個体の死に導いている。
3.2500年前まではヒトの寿命は15歳だった
旧石器~縄文時代(2500年前以前)には、日本人の平均寿命は13~15歳だった。この時代のヒトの平均寿命が、環境に左右され生活が安定していなかったこと、狩猟での事故死、そして何より病気や栄養不足による乳幼児の死亡率が非常に高かったために、他の霊長類よりも短かった。アクシデント的な死に方がメイン。人口も10万~30万人と変動が大きかった。全員が13~15歳で死ぬわけではなく、幼少期を生き延びたヒトは出産・子育てをして30代、40代までは生きていた。現在よりも多産で多死のこの状態が、進化を加速し、のちの人類の大躍進に繋がった可能性かもある。
弥生時代にはいると、日本人は稲作を始めた。食生活は狩猟中心の生活から定住型となり、安定はしてきた。乳幼児の死亡率も多少は改善され、平均寿命は20歳、人口は急激に増加して60万人。
平安時代には平均寿命は31歳、人口は700万人。続く鎌倉、室町時代には、天候変動による不作や政治の不安定化、それに「いくさ」などが頻繁に発生し、平均寿命は20代に逆戻り。室町時代の平均寿命は16歳。江戸時代に入ると、平均寿命は38歳まで延びた。
明治、大正時代の平均寿命は、女性44歳、男性43歳と延びた。戦争中は31歳となったが、戦後順調に回復し、現在(2019年のデータ)では、女性87.45歳、男性81.41歳で過去最高を記録。最近100年間で寿命がほぼ2倍に延長した。
4.ヒトの最大寿命は115歳!?
生存曲線を見ると、85歳くらいから急に下がる、「生理的な死」の時期を示している、老化による寿命。もう一つ分かることは、寿命は延びているが、最長の寿命(105歳付近)は余り変化していない。100歳以上の日本人は8万人を突破し、毎年急速に増え続けているが、115歳を超えた日本人はこれまでたったの11名、全世界でも50名にも満たない。ヒトの最大寿命は115歳くらいが限界。
B.そもそも生物はどのように死ぬのか
生き物の死に方には大きく分けて2つある。一つは、食べられたり、病気をしたり、飢えたりして死んでしまう「アクシデント」による死。もう一つの死に方は、「寿命」。遺伝子的にプログラムされていて、種によってその長さが違う。
大型の動物は「寿命死」が多く、小型は「アクシデント死」が多い。小さい生き物は、「食べられないことが生きること」、一方、比較的大きな生き物は自分の体を維持するために「食べることが生きること」。
今生き残っている生き物たちにおいては、その「死に方」でさえも何らかの意味があったからこそ、存在している。
1.老化しない、細菌的死に方
細菌が多細胞化の道を歩まなかった理由の一つは、ゲノムの構造にある。細菌のゲノムは輪っかのような環状で、この最大の利点は、テロメアを持たないことにある。テロメアとは、染色体の末端を分解から保護する役割を持つ特殊な構造。線状の染色体は必ず持っている。細菌のゲノムは複雑な構造のテロメアを持たず、サイズも小さいので、分裂に要する時間も短くて済む。次々に分裂して数を増やすためDNAに変異を持つ細胞の発生確率が高く、多様な性質を獲得して新しい環境に適応するまでの時間が短く、いろんな環境で生き残ることができる。
細菌は、基本的には栄養が続く限り永遠に増え、老化はなく、自然に死ぬ、いわゆる老衰死はない。細菌が死ぬ場合は、飢餓か被食、環境の変化などによるアクシデント死。
2.生殖で死ぬ、昆虫的死に方
カブトムシや他の昆虫にとって、大きくなれるのは幼虫の時だけ。つまり幼虫の仕事は、食って大きくなること。軟らかいイモムシのような幼虫は、モグラの大好物で、食べられて死ぬ。成虫に比べると無防備、行動範囲も狭い。そこで、より運動性が高く捕食されにくい硬い体を持った「成虫」になるように進化した。交尾のために変態する。
多くの昆虫は、交尾の後、役割がすむと死ぬ。成虫の寿命は、子孫を残すためだけに使われる。無駄に生きないという意味では、積極的な死に方であり、進化したプログラムされた死。
3.食べられて死ぬ、マウス的死に方
実験室で飼うと2~3年生きるが、野生では数ヶ月から1年。ハツカネズミは生後2ヶ月で成長・成熟し、20日間の妊娠期間で4~5匹の赤ちゃんを出産する。どうせ食べられて死ぬので、長生きは必要がない。小型のネズミは長生きに関わる機能、例えば抗ガン作用や抗老化作用に関わる遺伝子の機能を失っている。
ヒトの老化を研究するためにマウスをモデル動物として採用するのは、ヒトとマウスの死に方は違うのであまり良くない。
4.大型の動物の死に方
大型の動物は、長寿命。
哺乳類の場合は、体を構成する細胞の大きさは変わらないので、大きな体を作るためには多くの細胞が必要。発生の段階でたくさん細胞分裂をして、その数を増やす必要があるので、そのための時間がかかる。大型の動物は大量の食料を必要とするので、自力で食糧の確保ができなくなったら、もはや生きていけない。
5.ヒト以外の霊長類の死に方
体が大きい種類ほど長生き。基本の死に方は、“ピンピンコロリ”。ヒトのような長い老後はない。
C.そもそも生物はなぜ絶滅するのか
1.生命の誕生と多様性
最初はたった1つの細胞が、偶然地球上に誕生した。現存している生き物は、DNAを遺伝物質としてタンパク質を合成するといったシステムが共通しているので、元となったオリジナルの細胞は1つだと考えられる。
原始の細胞の中で効率良く増えるものが「選択」的に生き残り、また「変化」が起こり、いろんな細胞ができ、さらにその中で効率良く増えるものが生き残る。この「変化と選択」が繰り返された結果、多様な細胞(生物)ができた。遺伝子の変異と絶滅(死)による選択が、多様性を支えている。
死んだ生物は分解され、回り回って新しい生物の材料となる。新しい生物が生まれることと古い生物が死ぬことが起こって、新しい種ができる「進化」が加速する。
①絶滅による新たなステージの幕開け
生命の誕生と多様性の獲得には、個体の死や種の絶滅といった「死」が重要である。つまり、「死」も進化が作った生物の仕組みの一部。
実際にはゴールがあって進化したわけではない。多様な種のほとんどが絶滅、死んでくれたおかげで、たまたま生き残った「生き残り」が進化という形で残っている。恐竜の次に哺乳類の時代へと移ることができた。絶滅による進化が、新しい生き物を作った。
②そもそも多様性はなぜ重要か
様々な種が存在して生態系が複雑であればあるほど、ますますいろんな生物が生きられる。A種が絶滅したとしても、それと似た生活スタイル「ニッチ」を持つ生物が代わりをするので、大きな問題は起こらない。絶滅で生じるロスが生態系に吸収される。健全な生態系のバッファー効果と言っていい。
しかし、ヒトの活動の影響で多量に、しかも急激にいなくなると、似たようなニッチの生き物が抜けた穴を補うことができなくなる。そうすると、さらに絶滅した生き物に依存して生きていた生き物も絶滅する。ドミノ倒し的に、あっと言う間に多くの生物が地球から消えてしまう。
2.メジャーチェンジからマイナーチェンジ
細胞は、炭水化物を燃やしてエネルギーを作るが、その時に出る活性酸素によってDNAは酸化する。例えばグアニンは2本鎖になる時にシトシンとペアを作るが、酸化したグアニンはアデニンとペアを作ってしまう。つまりDNAの複製時に配列が変化し、遺伝情報が変わってしまう。
DNAの脆弱な性質は、生命誕生の初期に多様性を作るという観点では、プラスの面が大きかった。しかし、細胞の機能が複雑化してくると、細胞を位置から作り変えるような全面的な変更では、効率の良い「増殖マシーン」を作りにくくなった。
時代は、激しく変化する“ガラガラポン”(メジャーなチェンジ)の時代から、いい機能は残しつつマイナーなチェンジをする時代へと移っていった。このマイナーチェンジの時代は今でも続いている。
①最後のメジャーチェンジ その1 真核細胞の出現
細菌は「原核生物」と呼ばれ、核やミトコンドリアなどの細胞内小器官を持たないシンプルな作りの細胞。そのシンプルさ故に細菌の増殖速度は他の生物に比べ並はずれて早く、適応能力に優れ、地球上の至る所に生息している。
原核細胞に最後のメジャーチェンジ的な2つの変化が起きた。1つ目は、共生による「真核細胞」の誕生。DNAは核に収納され、酸素呼吸を行うミトコンドリアや、あるものは光合成を行う葉緑体を持っている。何種類かの原核細胞が融合して作られた。
ミトコンドリアは、もともと酸素呼吸を行うプロテオバクテリアという細菌だった。現在全ての真核細胞はミトコンドリアを持ち、酸素呼吸が行えるようになっている。
葉緑体はもともと光合成によって酸素と栄養を作るシアノバクテリアという細菌だった。これが共生した細胞はやがて植物細胞になった。現在も単細胞の真核細胞として、ゾウリムシやミドリムシとして生きている。
②最後のメジャーチェンジ その2 多細胞生物の出現
真核細胞はより効率良く栄養を作ることができるように、2つ目のチェンジ「多細胞化」が起こる。
地球全体の環境は、生物に優しい環境に近づいてきた。細胞は、生活環境の違いで2つの分かれ道があった。
一つは昔とあまり変わらない環境に棲み続けて、そこから離れられなくなったもの。現在でも、例えば海底の熱水が噴出するような原始の地球に似た環境に生息する生物。大昔の姿のままで存在している。
もう一つは、他に追いやられた細胞。ランダムに変化して、そこの環境に合わせて多様な性質を獲得したものが生き延びた。その内の一部は、分裂で増えた真核細胞が集合体を作り寄り添って生活を始めた。最初は単なる塊だったが、それぞれの細胞が集団の中で役割を持ち始めた。これが「多細胞生物」の始まり。
③細菌が持つ多様性の仕組み
大腸菌には染色体とは別にF因子という小さなDNAが存在する。時折、F因子は染色体の中に組み込まれて、そこでDNAの複製が開始される。
さらにF因子は接合繊毛と呼ばれる糸状の細胞同士を繋ぐ構造体の遺伝子を持っており、それによって他の菌と繋がる。F因子からのDNA複製によるコピーは、繊毛を伝ってF因子を持たない菌に移動する。F因子による遺伝情報の交換は、性分化の最も初期のタイプと考えられている。
④多様性を生み出す「性」という仕組み
体の構造が複雑になると、マイナーチェンジの多様性を生み出す有性生殖の仕組みを持つ生物が選択されて生き残った。雄と雌がいる「性」という仕組み。
- カテゴリー
- 進化・生物多様性

