このオムライスに、付加価値をつけてください
2025年10月09日(木)
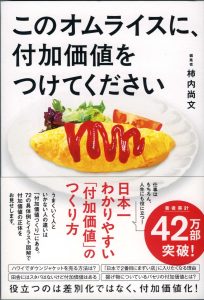 柿内尚文著
柿内尚文著
2025年2月27日発行
ポプラ社
1500円
付加価値をつくることができると、人生を豊かにおもしろく変えることができる。付加価値を知ることは、仕事にも、人生にも、大いに役立つ。何を優先すればいいか、何を目標にすればいいか、どんな行動をしたらいいかなど、人生や仕事の指針を作ることにもつながる。仕事を人生を、新たな視点で捉え直し、自分の強みを見つけ新しい一歩を踏み出そう。
仕事は「付加価値をつくる」ことと「作業する」ことに分けられるが、成果につながる付加価値をつくることが評価されやすい。作業する時間よりも付加価値をつくる時間を増やしていくことが、自分ならではの仕事をすることになる。
A.価値には、既存価値、付加価値、不要価値の3つがある
既存価値 想定内の価値
付加価値 想定外の価値
不要価値 付加価値になっていないこと
価値を考える時に、付加価値とは何かを知ることが、既存価値、不要価値を知ることになる。
B.付加価値とは何か
想定を超える値打ちが付加価値。「付加されたもの=付加価値」とは限らない。不要価値になっているものもある。
スーパーのレジ打ちの「既存価値」は「スピーディーに会計を進められること」。人気の店員さんにレジを打ってもらうと、いい気分になる。これが「付加価値」。思っている以上の喜びをお客にもたらしている。
a.想定内か想定外かを決めるのは、「価値を受け取る側」
店主がこだわって仕入れている美味しいお肉を長年のやり方を変えずに同じように売っていた肉屋さんは、お客のニーズに合わなくなっていったから徐々にお客の数が減っていく。一方で長年人気を保っているお肉屋さんは、料理をするのが面倒な人向けに総菜を増やしたり、油っぽいものが苦手な人でも食べやすい総菜の品数を増やしたり、お客のニーズに合わせて変化をしている。
人気がなくなってきたお肉屋さんは、付加価値ではなく、既存価値で商売している。うまくいっているお肉屋さんは、付加価値を作り続けている。人は、「付加価値」を買っている。期間限定、その場でしか買えないなどの付加価値が、興味を生み、購入へとつながる。付加価値があるものは人気になり、付加価値のないものは人気がなくなる。
b.付加価値はどんどん変化していく
昨日の付加価値が今日の付加価値とは限らない。時間経過と共に変化するのが付加価値。
ブームは、3つの価値の変遷で成り立つ。
ブームになり始め →付加価値
ブームの途中から終盤→既存価値に移行
ブーム終焉 →不要価値に移行(もしくは既存価値のまま)
ブームは、付加価値→既存価値→不要価値、という道を歩むが、定番化はブームで終わらず既存価値でとどまったもの。定番も大切。
c.伝わらなければ、付加価値ではなく不要価値
お店は、パセリを「付加価値」だと思って洋食のお皿にわざわざ付けていても、理由を知らない、知っていてもうれしくなければ、それは「不要価値」。注文したのはコロッケやトンカツ、エビフライなので、パセリがなくてもメニューは成立するから「既存価値」にはならない。
パセリが付け合わせに出てくる理由は、
・見た目の彩りをよくするため
・パセリに含まれる成分に殺菌効果、消化促進効果、消臭効果があるため
・食べても美味しいから
メニューの片隅に書いて伝えれば、お客にとってパセリの価値が変わり、食べ残す人も減るのではないか。
C.自分の付加価値をつくる
ただ言われたことだけをやり続けていると、付加価値を提供するのが苦手になってしまうリスクがある。
1.うまくいく人、いかない人
うまくいかない人は付加価値をつくることよりも、目の前のことやすぐできること、やりやすいことを優先する。優秀な営業マンは、目の前の結果にとらわれない。すぐに結果を出そうとすれば売り込みになってしまう。時間軸を未来に向けて、付加価値を積み重ねていくことが、結局は成果に結びつく。
2.付加価値が見つかる「自分への問い」
自分の悪いところを見つけて悩むより、付加価値になるところを見つけてそこを磨くほうが、心にもいいし、人にも伝わりやすい。「差別化」ではなく「付加価値化」。
成功視点を身につけるには、自分への問いかけが重要。大切なのは、付加価値化を軸に考えること。脳は与ええられた問いに正解を探そうとする特性があるから、ダメなところが見つかる「どうして売れないのか」ではなく、付加価値が見つかる「どうしたら売れるのか」へ「自分への問い」を変えること。
3.付加価値を生み出す
上司から「この件を任せた」と頼まれ、仕上げて上司に提出すると、「これじゃダメだ。やり直し」と言われた。ここでのポイントになるのが、「任せる」の定義。あなたにとって「任せる」は、自分の考えで進めることだと思ったが、上司は付加価値を生み出すという意味で使っている。あなたの提出したものに対して「付加価値があるとは思えない」からやり直しになった。
D.付加価値づくりの達人
すごい人は、付加価値をつくるのがうまい。
一見マイナスに思えることをプラスに変える技術を持っている人。僕らには付加価値があることに気づいていないが、既にあるものの中に付加価値を発見できる人。
すごい技術、「ポジティブ価値化」とは、「一見ネガティブに思えることに対して、視点を変えてポジティブ化していく方法」。
付加価値になっているか、不要価値になっているかを見極めるポイントは、対象になる人がそこに自分なりの意味を発見できるかどうか。発見できれば付加価値に、発見できなければ不要価値になる。
人は無意識でいると悲観的に考えがちで、楽観的に考えるには意志が必要。いい情報よりもマイナスな情報のほうが人に伝わりやすい。ネガティブ、マイナスなことは自分の生命を脅かすリスクにもつながるので、感知能力が高い。
E.付加価値をつくる技術
a.「視点」を変える
普通のものでも「視点」を変えることによって、相手によって、場所を変えることによって付加価値が生まれる。
日本人からすると「普通のもの」「当たり前のもの」でも外国の人が見たら「付加価値」になる。電車が時間通りにくる、飲食店でおしぼりや水やお茶がでる。
このオムライス食べたいという軸だけではなく、話したい、思い出になる、健康のためなど、視点を広げるとオムライスの付加価値がどんどん生まれる。
b.再定義化
階段を通路としてだけではなく、運動器具として捉え直す(再定義化)ことで、付加価値が生まれる。「1段上がるごとに0.1キロカロリー消費する」という表記すれば付加価値になる。新しい価値を提供することが付加価値。
c.小話プラス
ちょっとした話、「興味がわきやすくなること」と「記憶に残ること」をプラスするだけで、既存価値も付加価値に変化させることができる。
友人を誰かに紹介する時に、その友人とのエピソードを盛り込んで紹介する。対象に対する解像度が上がり、理解度も上がり、興味や関心を生みやすくなる。
d.プロローグ化
付加価値をつけたい対象を盛り立てるための前ふりになるストーリーをつくること。
意識的にマイナスの話を入れること。いい話ばかりを集めてしまうと、人の心には刺さりにくい。マイナスが大きければ大きいほど、プラスも大きくなり心に響く。
e.インパクト化
ネガティブ表現を活用する時は、ネガティブで終わらせない工夫があれば、より付加価値が届きやすくなる。
「ネガティブ表現」+「でも」+「プラス表現」
この型を使うことでインパクトのある表現をつくることができ、付加価値がより伝わりやすくなる。
f.「ちょい付加価値」で満足度アップ
「おいしさ200%」ではなく、「3割うまい」に「ちょい付加価値」を感じる。期待感を上げてしまうと、マイナス付加価値になってしまうリスクがある。言い過ぎるとハードルが上がってマイナス効果になりかねない。「ちょい付加価値」を数多く提供できれば、積もり積もって大きな付加価値になっていく。
- カテゴリー
- 働き方

