ウイルスは生きている
2020年10月28日(水)
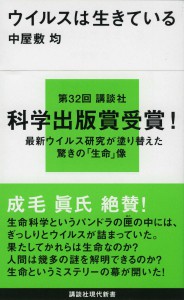 中屋敷均 著
中屋敷均 著
講談社現代新書
840円
2016年3月20日発行
教科書では「ウイルスは生物ではない」と教えられる。しかし、細菌で起こる病気もウイルスによって起こる病気も、基本的には同じ生物現象にしか思えない。そして、「ウイルスDNA」を、たった1塩基変異させただけで感染しなくなり、「ただの物質」となる。DNAのたった1塩基の違いが、「生き物」と「ただの物質」を分ける。
我々人間は異なった2つの「生」を生きている。DNA情報からなる生物「ヒト」としての「生」と、脳情報からなる人格を有した「人」としての「生」。例えば、不慮の事故に会う。すぐに精子を取り出し冷凍する。人が亡くなった後でも、細胞としての精子は「生きて」おり、そこから子供が生まれてくる。「ヒト」は生きていても、「人」は亡くなっている。多くの生物は、DNA情報による「生」しか持たない。
1973年6月28日発行福見秀雄著「ウイルス その生態と進化」
kojima-dental-office.net/blog/20201009-14315
2007年5月20日発行福岡伸一著「生物と無生物のあいだ」
kojima-dental-office.net/blog/20200914-14306#more-14306
1.生命の鼓動
試験管内自己複製系により生命の起源を探求してきた、この分野の第一人者とも言えるジェラルド・ジョイスは、生命の定義について「生命とはダーウィン進化する能力を持つ、自続的な化学システムである」とした。この言葉はNASAによる「生命の定義」にも採用されている。
「利己的な遺伝子」を著したリチャード・ドーキンスは、生物のダーウィン進化とは、生物そのものではなく、物質(DNA)が受けるのであると考えた。その環境下で増殖できるものが増え、より安定して効率よく増える方向へと変化していく。
生命の起源は単純な化合物が徐々に高分子化して誕生したとする「化学進化説」が有力な仮説として考えられている。生命は物質から進化してきたことになり、物質と生命とは原則的に連続している。もしそうであるなら、生命の初期においては、リボソームを持たないこともATPを作れないことも、当然のことである。自己の代謝系を持たない初期生命は、それらすべてを外部の環境に依存していたと考えざるを得ない。
「生命」は40億年の進化の過程で、「代謝」を環境に依存した状態からより多様な環境下でもその維持が可能となるように少しずつ進化していった。
ウイルスに言わせれば、自ら代謝せずともそこに自らの存在を維持できる環境があれば、それを利用して増殖して、一体何が悪いのか?ヒトだってアミノ酸を作れないだろ、となる。ヒトは、「生命に必要な代謝系」のすべてを保有していない。大腸菌などの細菌や植物がすべてのアミノ酸を合成できるが、ヒトは生命活動の基本とも言える必要なアミノ酸20種ほどのうち9種を欠いている。それを自分の周囲の環境から捕食により取り入れることにして、その合成のための代謝系を放棄してしまった。つまり、ヒトは自己の維持に必要な代謝系の一部を外部環境に依存しており、決して自己完結していない。体の中には多数の腸内細菌がおり、その助けを借りて生きている。各細胞の中には、独立した細菌であったミトコンドリアがいて、ゲノムDNAの半分はウイルスや転移因子等である。
2.ホストジャンプ
ウイルスが変異して新しい宿主への病原性を獲得すること。人類は生物進化の歴史ではほぼ最後尾に登場しており、ヒトに感染するウイルスは他の動物からのホストジャンプによって病原体となったと考えられている。
ホストジャンプを起こしたウイルスが、その初期に新しい宿主を殺してしまうのは、その宿主上でどのように振る舞ったら良いのか分からない「憂えるモンスター」が自らの力を制御できず、暴れているに過ぎない。
ウイルスの毒性が低下するということが、長い目で見た場合には一般的であったとしても、短期的には強毒型へとウイルスが変異する例も多く知られている。
弱毒化は、感染した宿主の行動時間が長くなり、新たな感染の機会が増える、というウイルス側の適応進化が起こったと解釈されるべき現象だろう。「スペイン風邪」の毒性も、パンデミックの発生から数年で大きく低下したことが報告されている。ウイルスそれ自体の致死率も大幅に低下している。
①スペイン風邪
通常のインフルエンザでは乳幼児やお年寄りの死亡率が高いが、スペイン風邪では見るからに健康そうな20代から30代の青壮年者が次々と感染して犠牲となった。数時間前まで元気な健常者が突然発熱して全身に痛みを訴え、口や鼻から血を流すようになり、次の日に亡くなった。
第一次世界大戦で犠牲となった死者数は、1914年~1918年の4年間で戦闘員が約850万人、非戦闘員が約650万人。期を同じくして人類は1918年~1919年にもう一つの未曾有の脅威、世界的に流行した「スペイン風邪」と対峙した。当時の世界人口18億人のうち、約3割の6億人が感染し、推計2000万人~5000万人もの人が命を落としたと言われている。中国やアフリカなどにおける感染死亡統計が正確に含まれていないことから、実際には1億人に達していたとの推定も出されている。
80年後の1997年、米国陸軍病理学研究所のジェフリー・トーベンバーガーらは、アラスカの永久凍土で得られたウイルスの遺伝子解析から、1918年の「スペイン風邪」が、鳥インフルエンザウイルスに由来するものであったと結論づけた。H1N1型のインフルエンザウイルスは鳥に感染することが多く、ウイルスが変異して初めてヒトに感染した。その当時の人々にとって、今までにない「新しい敵」であった。
②エボラ出血熱
病原体であるエボラウイルスは、もともと自然界でコウモリを宿主としていた。ヒトに感染した場合には、致死率が50~80%にも上るという恐怖の殺人ウイルスであるが、天然の宿主であるコウモリの中では、特に目立った病気を起こさない。
③ウサギ粘液腫ウイルス
元来オーストラリアにはウサギは生息していなかったが、1859年に英国人トーマス・オースティンが狩猟の対象とするために24羽のウサギをイギリスより持ち込み、オーストラリア南東のビクトリア州で野外に放した。ウサギは繁殖力が強く、天敵が少ないなどの好条件も重なり、爆発的に増殖し、1920年にはオーストラリア全土で生えている草を食い尽くし、重要な産業である牧羊や農業にも深刻な打撃を与えるようになった。
そこで考えられたのが、ウサギ粘液腫ウイルスによって駆除する方法。このウイルスは研究室でウサギの致死率が99.8%にも上るという強毒性ものであり、1950年にこれを用いたウサギ駆除作戦が大々的に実施された。当時6億羽程度と推定されたが、その90%がこのウイルスにより駆除された。しかし、その成果もつかの間、ウイルスによる致死率が徐々に低下し始めた。6年後のウイルスを実験室系統のウサギに接種してみると、致死率50%前後に低下していたことが明らかになった。実験に使われたウサギの遺伝的な性質はまったく同じであり、ウサギが強くなったのではなく、ウイルスの毒性が低下していた。
3.宿主と「一体化」しているウイルス
われわれの体は、自分を守るために高度に発達した免疫システムにより、体内にある「非自己」はその激しい攻撃の対象となり排除される。しかし、母体の子宮は不思議な場所。胎盤という組織に守られて、子宮の中に「別の生命」が生きている。例えば、母親の血液型がO型で、お腹の中の子どもの血液型がB型であっても、胎児は攻撃対象とはならず、母親の血液を介して酸素や栄養分を受け取り、すくすくと育っていく。
胎盤の絨毛を取り囲むように存在する「合胞体性栄養膜」は胎児に必要な酸素や栄養素を通過させるが、非自己を攻撃するリンパ球等は通さず、子宮の胎児を母親の免疫システムによる攻撃から守る役目を果たしている。
2000年の「ネイチャー」誌に驚くべき論文が掲載された。「合胞体性栄養膜」の形成に重要な役割を果たすシンシチンという蛋白質が、ヒトのゲノムに潜むウイルスが持つ遺伝子に由来すると発表された。胎児を母体の中で育てるという戦略は、哺乳動物の繁栄を導いた進化上の鍵となる重要な変化であったが、それに深く関与する蛋白質がウイルスに由来するものだった。
ある時ウイルスは我々の祖先に感染した。そしてシンシチンを提供するようになり、今も我々の体の中にいる。そのウイルスがいなければ胎盤は機能しなかった。我々の体の中にウイルスがいるから、我々は哺乳動物の「ヒト」として存在している。我々は既にウイルスと一体化しており、親から子へ「ヒト」の遺伝子だけではなく、感染したウイルスからも遺伝子を受け継いでいる。
シンシチンは母親の免疫系による攻撃を保護する合胞体性栄養膜の形成に重要な働きをする。子宮の中の胎児は羊膜に包まれ、へその緒を介して母親の胎盤と繋がっている。そのへその緒の先は、植物の根のように枝分かれした絨毛と呼ばれる組織となっており、この胎児の絨毛が母親の胎盤に根を張ることで母と子が連結されている。この絨毛の表面を覆うように存在しているのが、合胞体性栄養膜である。役割は2つ。物理的な細胞形状の変化による防御と免疫抑制作用。この構造は単なる膜ではなく、多くの細胞が次々と連結し、細胞融合を繰り返した巨大な1つの細胞となった層である。この細胞には多数の核が存在する。細胞融合を起こさせる蛋白質がシンシチンであり、シンシチンはレトロウイルスが持つenvという遺伝子に起源をもっている。
血球細胞の中には、例えば白血球が血管の壁をすり抜けて生体組織に入っていくように、細胞と細胞の隙間を通過する能力に長けているものが多くある。しかし、この合胞体性栄養膜はそのような細胞の隙間がない巨大な一枚岩となっているため、すり抜け能力の長けた免疫細胞であっても胎児側に侵入することを難しくしている。
4.研究者としての特徴は「枠を突き抜けた純度の高さ」
植物の中で増殖し、病気という生命現象を引き起こすTMV(タバコモザイクウイルス)というウイルスが、ただの物質のように結晶化する存在であることを示したロックフェラー研究所の生化学者ウェンデル・スタンリーの発見は、生命科学史上、特筆に値するものであった。その発見が与えた最大の驚きは、生命と物質の境界を曖昧にしたことである。成長する、増殖する、進化するなどの属性は生物に特有なもので、生物と物質とは明確に区別できるという常識が大きく揺らいだ。ウイルスは純化すると、ただの蛋白質と核酸という分子になってしまう。しかし一方、生きた宿主の細胞に入ると、あたかも生命体のように増殖し、進化する存在となる。
1935年に「サイエンス」」にスタンリーは、「濾過性病原体」の正体を蛋白質であることと、TMVの結晶にはリンも糖も含まれていなかったと発表した。実際には蛋白質の他に核酸の一種であるRNAが5%含まれている。当時の分析技術の感度の低さに加え、思いこみも作用していた。彼も「時代の意識」に飲み込まれていた。
1936年に「ネイチャー」にイギリスのフリードリック・ボーデンとノーマン・ピリエは、精度の高い解析結果を報告している。TMVの結晶は、95%の蛋白質と5%のRNAを構成成分として持つ核酸蛋白質であるとした。RNAこそがウイルスの「本丸」であることが示されたのは、さらに20年の歳月が流れた1956年のことになる。
その間に、1944年にオズワルド・アベリーらの実験により遺伝物質の本体がDNAであることが示され、1953年にワトソンとクリックのDNA二重らせんモデルが提唱される。
5.ウイルスの基本的な構造
ウイルスは細胞膜に囲まれた細胞構造を保有せず、蛋白質を合成するリボソームも持たないが、固有の遺伝情報からなる核酸を保有している。そのゲノム核酸をキャブシドという蛋白質の集合体で包んでいる姿が、ウイルスに共通する基本構造。ウイルスにも多様性があり、基本構造に準じないものや様々な付加的な構造を持つウイルスも実際には存在している。付加的な構造のうち、比較的多くのウイルスに共通して持っているものにエンベローブがある。これは、ゲノム核酸とキャブシドの外側を包む脂質膜構造である。ウイルスは感染した細胞から外に出る時に、宿主の脂質膜をはぎ取ってこの構造を作る。
エンベローブはリン脂質からなる細胞膜でできているので、その構造を壊してしまう石鹸に弱く、エンベローブを持つウイルスは、石鹸による予防が効果的である。インフルエンザの予防には石鹸で手を洗うことが勧められているが、これはインフルエンザウイルスがエンベローブを持ち、この構造が破壊されると感染力が著しく低下するからである。一方、胃腸炎を起こすノロウイルスは、エンベローブを持たないため石鹸の効果がない。
6.DNA→RNA→蛋白質
ゲノムをDNAとすると、情報を発現するためには必ずRNAを作らなければならないが、RNAウイルスはDNAからRNAを作るステップを省略でき、合理的で効率がよい。植物ウイルスや菌類ウイルスでは、そのほとんどがRNAウイルスである。重症急性呼吸器症候群の原因となるコロナウイルスのゲノムサイズは3万塩基くらいである。3万塩基くらいにRNAウイルスの大きさの限界があるように見える。
RNAという分子はDNAと比べて、その分子構造から化学的な反応性が高いという性質を持っている。しかし一方、反応して違う物に変わってしまう可能性も高く、物質としての安定性がDNAより低いという欠点に繋がってしまう。また、RNA複製酵素はDNA複製酵素に比べてエラー率が高く、複製時の突然変異が起きやすい。
ゲノムが大きくなると、高い変異率が致命傷になってしまう。致命的な突然変異が10万分の1の確率で起こるとすると、ゲノムのサイズが100万塩基になれば、確率的に1回の複製で10カ所にも致命的な変異が起こる計算になる。とても継続的に子孫を残していくことはできない。ウイルスが、効率の良いRNAをゲノムとして用いることができるのは、彼らのゲノムサイズが小さいことと無縁ではない。
逆に言えば、細胞性生物は2本鎖DNAをゲノムとしたことで、ゲノムを大きくすることが可能となり、より多くの遺伝情報を用いた複雑な仕組みを作る方向へと進化していった。
7.抗体の多様性
ヒトを含む脊椎動物(有顎類)は病原菌等の侵入に対して、他の生物では見られない強力な防御機構、獲得免疫を有している。感染が一度起こると、抗体というタンパク質分子を用いてその病原体の分子パターンを記憶し、次に同じ病原菌による感染が起こると素早く強力な抵抗性を発揮する。抗体は、敵の小さな違いも認識し、特異的結合するものができてくる。ヒトが作り得る抗体は100億種類を超えるという推計もある。ヒトゲノムに存在する遺伝子の数は2千万個ほど敷かなく、1つの遺伝子から1つの抗体が作られるとすると、数が合わない。この謎を解いたのが、1987年にノーベル生理・医学賞を受賞した利根川進であった。抗体分子の「可変部」ができあがる過程に制御された遺伝子配列の組み替えが関与することを発見した。「生まれたて」の受精卵やそこから発生してくる分化初期の細胞たちが持つ遺伝子配列を見ると、V領域が50個程度、D領域が30個程度、J領域が6個程度、反復して存在した形となっている。
特定の抗体を作るB細胞へと発生が進み、成熟していく際に、V領域から1つ、D領域から1つ、J領域から1つと、反復されている配列から各1つが選ばれ、それらが結合した可変領域の遺伝子ができあがることになる。これがV(D)J再構成と呼ばれる、抗体の多様性を生む機構である。
2007年の「ネイチャー」に、潜伏感染しているヘルペスウイルスの影響で、病原細菌であるリステリア菌やペスト菌の感染に対してマウスが強くなっていることが報告された。潜伏感染により免疫を活性化する作用のあるインターフェロン生産が増え、マクロファージが全身にわたって活性化されるなど、自然免疫が高まった状態となっていた。
8.水平移行
1999年の「サイエンス」にフォード・ドリトルが「生命の樹」を発表する。遺伝子は時に、同時代に存在する他種の生物同士間でやりとりされることがある。腸管出血性大腸菌O157は、無害で病原性のない大腸菌と比べると、ゲノム配列が約20%増加していた。他の菌から水平移行してきた、出血性大腸炎を引き起こす主な原因となるベロ毒素の遺伝子が含まれていた。ベロ毒素1は赤痢菌が産生するシガ毒素と同一のものであった。λファージは、その昔赤痢菌に感染した際にウイルス配列内に獲得していたもの。毒素遺伝子のλファージと別のファージがウイルスを介して別々にO157に運び込まれた。
抗生物質の耐性遺伝子をファージが持ち込むことにより、細菌が体制化する例も報告されている。ウイルス感染が細菌の性質を大きく変えた事例も多い。
- カテゴリー
- ウイルス

